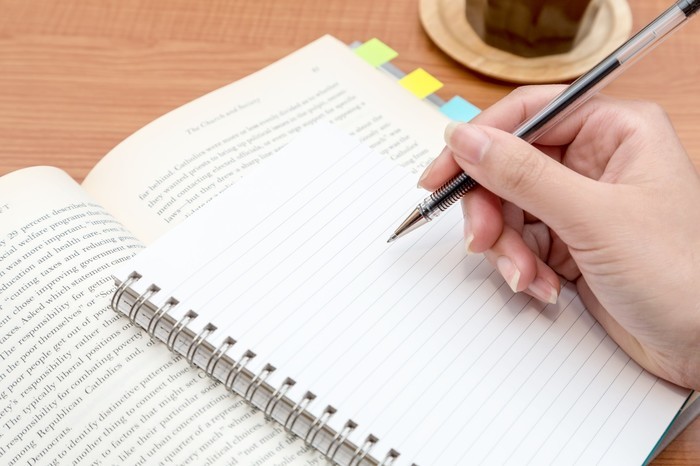[allpage_toc]
毒物劇物取扱責任者の試験の難易度・勉強方法
試験に合格し、毒物劇物取扱責任者の資格を取得すると、毒物や劇物の製造業は販売業などにおいて、貯蔵設備の管理や事故時の措置などにあたります。
法律に基づき、厳格な管理監督の元、責任を持って、毒物劇物を管理する立場としての、個の資格試験の、難易度や勉強方法、あるいは勉強に必要な時間とは、どのようになっているのでしょうか。
毒物劇物取扱者試験の受験資格など
受験料も都道府県によって、若干誤差がありますが、それでも、概ね1万円強といった受験料といったところです。また、試験実施機関が都道府県とはなっていますが、受験地と違う都道府県へ行っても、資格そのものは有効ですので、試験の難易度が低いと思われる、近隣の都府県へ赴いて受験する方法も、手っ取り早く毒物劇物取扱責任者資格取得を目指す、手段のひとつと言えるでしょう。
毒物劇物取扱責任者試験の難易度
実地試験は、「毒物劇物の取り扱い方法」と「毒物劇物の識別」の2つで、都道府県によっては、実技試験で実施する場合と、ペーパー試験で実施する場合とに分かれます。実技試験よりも、ペーパー試験を採用している自治体の方が増えていますので、実地試験の難易度は気にしなくても良いでしょう。
合格基準は、「総得点について満点の60%以上の得点率」であること、あるいは、都道府県によっては、前述の基準に加えて、「各科目40%以上の得点率であること」が条件となる場合があります。試験の難易度は、初級から中級レベルといったところでしょう。
都道府県別の毒物劇物取扱責任者試験の難易度
神奈川県
また、出題される問題数も100問と、近隣の都県と比べると多めに設定されており、正解すべき問題数から考えた場合、他の都県と比べ、高めと予想しておいたうえで、試験に臨む方が良いでしょう。
試験対策として、過去問を参考に、文章形式で毒物や劇物の特徴をおぼえることや、問題数の多さから、解ける問題は落とさないよう、心掛けましょう。
また、択一式で回答する場合でも、基礎化学では、炎症反応やモル式、周期表からの出題などもありますので、高校生レベルのな、化学の勉強が必要な難易度となっている傾向が見受けられます。
東京都
試験の出題傾向は、出題された例文について、正誤(正しいか誤っているか)の組み合わせを回答する形式が、多く見受けられます。また、出題された問題について、正しいものを一つ回答する、択一式の出題形式も多く見受けられます。
試験対策として、出題範囲の分野に関する、テキストを反復学習することや、過去問に挑戦することも、もちろん重要ですが、出題された問題文に対する、読解力も必要となって来ます。したがって、過去問を解く場合でも、問題文にどんなことが書いてあり、どんなことを回答すべきかを把握する練習も、行うとよいでしょう。
埼玉県
試験の出題傾向は、毒物劇物の法令に関する問題や基礎化学で、設問が穴埋め形式になっている、択一式の設問がいくつか見らます。穴埋め形式の設問は、試験勉強をきちんとしてさえすれば、回答できるとも割れる難易度ですが、勉強せずに試験に臨んだ場合は、難易度の上がることが予想されます。
「毒物劇物の識別および取り扱い方法」の設問では、問題文とは別に、毒物や劇物の特徴が記入された、選択肢の別紙があり、そこから、設問にある毒物劇物の特徴について回答する形式となっています。幅広く、毒物劇物の特徴について把握する必要がありますので、暗記の苦手な人にとっては、難易度の上がることも予想されます。
毒物劇物取扱責任者の難易度に対応する勉強方法
[no_toc]
試験対策
「毒物および劇物に関する法令」および、「毒物・劇物の性質および貯蔵方法その他取り扱い方法」については、テキストを見て覚えるという方法が必要となります。そのため、毒物劇物取扱責任者試験に関する参考書の購入は、必須となります。法規よりも、毒物・劇物の性質などに関する問題の方が、ウェイトの高くなる傾向が見受けられます。
また、都道府県によっては、ホームページなどで、毒物劇物取扱責任者試験の過去問を見ることもできますので、可能な場合は、参考にしてみましょう。
勉強時間
法規をおぼえることに対する難易度、化学の基礎知識に対する難易度、毒物や劇物をおぼえることに対する難易度などが、受験者の勉強時間を左右する試験といっても、過言ではありませんので、暗記や化学が苦手な場合は、少し多めの勉強時間を、想定しておいた方がよいでしょう。
独学は可能か
前述の項でも述べましたように、毒物劇物取扱責任者試験は、化学分野の知識と暗記力が物を、言う内容の試験となっています。したがって、化学分野の知識に長けている人や、暗記力に自信のある人にとっては、独学でも、資格取得は十分可能と言えるでしょう。
逆に、価格分野の知識に乏しい人や、暗記力に自身のない人の場合は、スタートラインが下がりますので、その分ハンデを背負うことになり、当然ながら、その分難易度も上がることが予想されます。その場合は、都道府県が実施する、毒物劇物取扱責任者試験受験者向けの講習会などがありますので、上手に利用するとよいでしょう。
毒物劇物取扱責任者試験は難関なのか
しかし、毒物劇物取扱責任者試験の合格率で見た場合、各都道府県間の合格率の差は、極端に大きなものではない傾向が見受けられます。とはいえ、試験対策については、受験先の都道府県の過去問とじっくり対峙し、その傾向と対策、および回答すべき内容などは、きちんと把握して臨むようにした方が無難でしょう。
毒物劇物取扱責任者試験に限らず、資格試験は、傾向と対策を十分に練って臨むことが、合格への近道となります。皆さんも、毒物劇物取扱責任者試験へ挑戦する場合は、受験する都道府県の試験内容を把握し、十分な対策を練って臨みましょう。