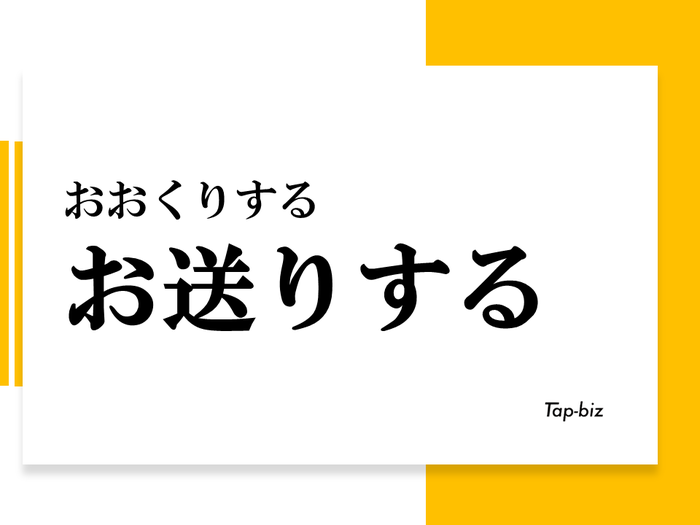[allpage_toc]
と不安になったことはないでしょうか?
メールや手紙などものを相手に送る時「お送りする」という表現を使います。これは敬語としてよく目にする言葉ではありますが、正しい使い方を知っていますか?
今回の記事では敬語としての「お送りする」の意味や使い方について説明します。また、注意点や英語での表現方法などもお伝えしますので、この記事を読むことで「お送りする」を正しく使うことができるようになるでしょう。
ぜひチェックして「お送りする」を使えるようになり、ビジネスシーンで役立てて下さい。
敬語「お送りする」の意味
まずは「お送りする」という言葉の本来の意味からご説明していきましょう。
「お送りする」は「送る」の謙譲語
「お送りする」は動詞の「送る」をつけて名詞形にし、「お~する」をつけることによって、敬語の謙譲語の表現にしています。
謙譲語は自分の行動をへりくだって伝えることで相手を立てる表現です。そのため、自分の行動にしか使えません。
すなわち、「お送りする」は「送る」の謙譲語であり自分の行動にしか使えない敬語です。
敬語「お送りする」の使い方・例文
そもそも「送る」という言葉は物だけではなく人などにも使えます。日常生活を送る中でよく使う言葉であるぶん、敬語としての表現を間違えて、失礼になってしまう可能性も高いのでしっかり確認していきましょう。
ビジネスシーンの場合
しかし敬語は言葉によって敬意の度合いが変化します。「お送りする」「お送りします」「お送りいたします」と順に敬意の度合いが上がっていきます。
「お送りする」のはこちらから相手に送るのであって、ビジネスシーンだとお客様や相手企業である場合がほとんどです。
「お送りする」だと敬語であっても非常にフランクな印象であるため、「お送りします」「お送りいたします」などを使う方がいいでしょう。
逆に同僚や親しい上司などであれば「お送りする」でも十分敬意は伝わります。
- お荷物をお送りします。
- 書類をメールでお送りしますのでご確認をお願いします。
メール・手紙を送る場合
また、「送付します」「送付いたします」としても問題ありません。
- メール(手紙)をお送りします。
- メール(手紙)をお送りいたします。
荷物を送る場合
「商品を発送します。」
「品物を発送いたします。」
また、上記のように「お送りする」を言い換えて「発送する」としても問題ありません。
- ご注文の商品をお送りいたします。
- ご依頼の品物をお送りします。
相手を目的地に送る場合
[no_toc]
また、「駅までご案内します」「目的地までご案内いたします」としても問題ありません。
- ○○様を駅までお送りします。
- ○○様を目的地までお送りいたします。
敬語「お送りする」の言い換え表現
使える場面はすべて「お送りする」を使っても問題ないですが、言葉のバリエーションが豊富なのが日本語の良いところです。
ここからは「お送りする」の類義語・同義語を確認していきます。語彙を増やしてより相手に伝わりやすい日本語を使えるようになってください。
「送付いたします」
「送付」自体が送り届けるという意味で、さらに「いたす」が謙譲語で「する」と言う意味になるため、謙譲語として使えます。また、相手に書類やデータをメールで送るという場合であれば「添付いたします」を使っても問題ありません。
ただし、書類などを添付せずにメールだけを送る場合は使えません。「メールを送信いたします」か「メールをお送りします」とするのが正しいので注意しましょう。
あくまで、メールの他に書類や画像など別データをつけて送る場合にのみ「送付する」・「添付する」が使えます。
- メールで書類を送付いたします。
- 郵便で書類を送付いたします。
「お連れいたします」
「連れる」は「同行者として一緒に行く」と言う意味の言葉です。これを「お~する」という形に変化させることで敬語の謙譲語として使えるようになります。
「同行する」という意味が「お送りする」より強いのでより分かりやすい表現です。
- ○○様を目的地までお連れいたします。
「ご一緒いたします」
どちらも「お送りする」よりもよりダイレクトに「同行する」という意思が組みとれる表現です。
また「ご一緒させていただく」としても誤りとはいえませんが、文脈によっては違和感がある場合もあるので「ご一緒いたします」とした方が自然です。
- 目的地までご一緒します。
- 目的地までご一緒いたします。
「送迎いたします」
もし「迎えにいく」という意味で敬語を使いたい場合は「お迎えにあがる」または「伺う」がふさわしいです。
誤って相手に伝えてしまうと混乱が生まれる言葉ですので間違えないよう気をつけましょう。
- 目的地まで送迎いたします。
[no_toc]
敬語「お送りする」の丁寧表現
一言に「お送りする」といっても日本語は変化が多く、「お送りします」「お送りいたします」と言い切りの形が変化します。ここからはこの変化についてさらに詳しく解説します。
「お送りします」
敬語を使うには言葉を向ける先を考える必要があります。
「お送りする」は、まず「お~する」に変化させて自分の行動自体をへりくだっていっていますが、「する」のままでは相手に向ける表現としては間違いです。
例えば自分だけが見る手帳などに「先生をお送りする。」と書くのであれば自分に向けている言葉であるため敬意は必要ありません。
言葉として声で発して伝える相手がいるのであれば、敬語を使いたい場合は「先生をお送りします。」とするのが正しいです。
複雑な部分ですが間違わないようにしましょう。
「お送りいたします」
丁重語の「いたす」を使うことで自分の行動をへりくだって伝えることで相手を立て、同時に相手へ向けた言葉としても丁重な表現になっています。くわえて丁寧語の「します」を足しています。
謙譲語の種類のうちの一つである丁重語と丁寧語の複合です。二重敬語ではなく正しい表現です。これは二重敬語が例えば丁重語と丁重語というような同じ意味の言葉が重なった場合を指すためです。
「~~いたします」は丁重な表現であるためビジネスシーンにふさわしく、よく使われますが、多用すると固い印象になりすぎることもあるので注意しましょう。
敬語「お送りする」の注意点
ここからは敬語「お送りする」をより正しく使う場合の注意点を細かく見ていきましょう。
「お送り致します」とは書かない
これは「致す」が補助動詞として使われ、本来の意味では使われていないからです。
本来「致す」には「届くようにする」または「結果を引き起こす」などの意味しかないため、単体では謙譲語ではありません。
別の単語とつながって文章中に出る場合のみ本来の意味ではなく補助動詞として扱われます。そのため敬語として「~いたします」と使いたい場合はひらがな表記にします。逆に動詞として使う場合は「致す」と漢字で表記するという決まりがあります。
「お送りいたします」という表記が正しいので間違わないようにしましょう。
「送らせていただきます」「お送りさせていただきます」は本来は許可が必要
しかしこれは不自然です。「送る」に「~させていただく」を足していますが、本来「~させていただく」を使うのは、自分が相手に対して行うことに相手の許可を得て、自分がその恩恵を受ける場合です。
例えば「仕事を休ませていただく」であれば自分が休むことに会社なり上司なり休むことに対する許可が必要で、その許可があることで実際に仕事が休めるので自分に恩恵があります。
「送る」という行動を取るのに相手の許可が必要ないかというと疑問が残り、完全に誤りであるとも言い切れません。しかし文脈に左右されたり、誤りであると感じる人もいたりするため、「お送りします」・「お送りいたします」とする方が無難です。
「送らさせていただきます」は誤用
「送らせていただきます」は、動詞「送る」+助動詞「せる・させる」+接続助詞「て」+動詞「いただく」+丁寧語「する」5つの言葉が合わさっています。この言葉を合わせるときには正しい形があり、法則があります。これを活用形と言います。
「送る」「いただく」は動詞で、この活用形は他動詞五段活用です。
また「せる・させる」は助動詞で、他の何かの動作をさせる場合に使う言葉です。「送る」と「いただく」をつげるために使っているのでこの場合は接続詞になります。
「せる・させる」を接続詞として使う場合、動詞は必ず未然形でしか接続できません。また「せる」は五段・サ変動詞に、「させる」は上一段・下一段・カ変動詞に使われます。
「送る」は他動詞五段活用であるため、未然形は「送ら」。五段活用であるため使う接続詞は「せる」です。ここからさらに助詞につなげるため、「せる」、「いただく」を連用形に変形し「せ」+「て」+「いただき」+「ます」となります。
このため日本語の文法から見て正しいのは「送らせていただきます」です。
活用を間違う不安があるのであれば「お送りします」か「お送りいたします」を使う方が無難です。
同僚・目上の人・取引先などで使い分ける
しかし「お送りいたします」とした方が敬意の度合いが高いので使う相手によって使い分けるのが望ましいです。
同僚や親しい上司であるば問題ありませんが、目上の人・取引先などであれば「お送りいたします」を使うのが無難です。
敬語「お送りする」の英語表現
[no_toc]
- 「I have attached ○○」(○○を添付します)
- 「I will send you ○○」(○○をお送りします)
- 「I am sharing ○○」(○○を共有します)
- →こちらはフランクな言い回しであるため同僚などに共有する場合に使います。
- ・「Could you review the attached ○○?」(添付の○○のご確認をお願いできますか?)
まとめ
今回の記事では「お送りする」について説明をしてきました。
日常生活において人に何かものを送ることはあるでしょう。よく使う表現だからこそ気を付けて言葉を選ぶことでお互いに気持ちよくコミュニケーションを取ることができます。
「お送りする」について確認してぜひ使いこなしてください。