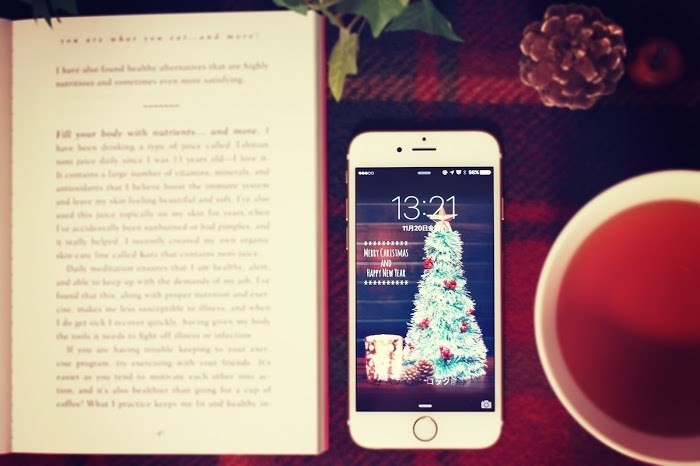[allpage_toc]
「お勤め」の意味と使い方
ここでは「お勤め」の意味について見ていきます。
「お勤め」の意味は?
お つとめ [0] 【御▽勤め】
①
「勤め」を丁寧にいう語。 「 -はどちらですか」
②
仏前で読経すること。勤行ごんぎよう。 「朝晩の-」
③
商人が客に奉仕すること。サービス。
④
遊女に払う遊興代。花代。 「げんなまでさきへ-を渡しておいたから/滑稽本・膝栗毛 初」https://www.weblio.jp/content/%E3%81%8A%E3%81%A4%E3%81%A8%E3%82%81
「勤め」を丁寧にいう語としての意味は?
「勤め」を辞書で引くと、以下のような意味があります。
つとめ [3] 【務め・勤め】
①
当然しなければならない事。任務。義務。 「国民としての-」
②
会社・官公庁などに雇われて,働くこと。また,そこでの仕事。勤務。 「 -を探す」 「 -に出る」 「 -をやめる」
③
毎日仏前で行う礼拝・読経(どきよう)。勤行(ごんぎよう)。 「朝のお-」
④
遊女の仕事。 「おもへば世に此道の-程かなしきはなし/浮世草子・一代女 1」
⑤
揚げ代の支払い。 「げんなまでさきへお-を渡しておいたから/滑稽本・膝栗毛 初」
当然しなければならない事
例えば「国民としての勤め」という使い方ですと「国民としての義務」という意味になりますので教育、労働、納税という国民の三大義務を指す言葉としても使えそうです。
会社などに雇われて働くお勤めの意味は?
辞書に例として紹介されている「お勤めを探す」は、雇ってくれる会社や官公庁を探す。「お勤めに出る」は会社や官公庁に出勤する。「お勤めを辞める」は会社や官公庁を退職する。という意味で使うことができます。
毎日仏前で行う礼拝・読経など
仏教の家庭では、毎朝(または昼、夜)、お仏壇の前でお経を読む習慣がある家庭も多いのではないでしょうか。例として紹介されている「朝の勤め」はそうしたお仏壇の前での行為を指します。「勤め」(=「お勤め」)は「義務」や「勤務」以外にも宗教的な意味にも使われています。
[no_toc]
遊女の仕事としての意味は?
その遊女の仕事も「お勤め」と言います。会社や官公庁で働く、という意味もありましたが、遊郭での仕事も「お勤め」です。
辞書の例にある 「おもへば世に此道のお勤め程かなしきはなし」は、遊郭での仕事ほど哀しいものはない、という意味になります。現在は金銭面の他、好きで働いている女性もいる職種ですが、昔は悪質な仲介業が存在して、騙されて働いていた女性も多いと言われています。
揚げ代の支払いとしての意味は?
「遊女の仕事」の他にも、その仕事への支払いも「お勤め」と言います。辞書で例にある 「げんなまでさきへお勤めを渡しておいたから」は、げんなま(現金)でさき(遊郭、湯屋など)へお金を支払っておいたから、という意味になります。
仏前で読経すること
辞書の例にある 「朝晩のお勤め」は、朝晩お仏壇の前でお経を読むこと、手を合わせることになります。
サービス
「勤め」の意味にあった、会社や官公庁などに雇われて働くこと、に近しい意味ですが、その中でも、商人をしている人の仕事内容が「お勤め」と言われます。飲食業や、小売業の、サービス業で接客をしている店員などを思い浮かべると分かりやすいのではないでしょうか。
「勤め」の意味にあった、遊女の仕事、にも近しい意味となります。遊女もサービス業であることに間違いないので、商人と言えるのではないでしょうか。
花代
辞書の例にある 「げんなまでさきへお勤めを渡しておいたから」も先ほど「勤め」の意味として出てきました。げんなま(現金)でさき(遊郭、湯屋など)へお金を支払っておいたから、という意味になります。
「お勤め」の使い方1「お勤めご苦労様です」
使う際の注意ですが、「ご苦労様」という言葉は、目上の人が目下の人を労わる言葉です。「お勤めご苦労様です」は目上の人に使うと失礼に当たります。部下や、後輩、またはお客としてサービスを受けた際に使うといいでしょう。
「お勤め」の使い方2「お勤めお疲れ様でした」
「ご苦労様」は目上の人に使うと失礼にあたる言葉でしたが、「お疲れ様」は目上の人に使っても失礼にはあたりません。(失礼にあたる言葉という考え方もありますが、今は「ご苦労様」に代わり「お疲れ様」は誰にでも使える言葉とする考え方が多いです。)
上司が退職する際や、退勤する際には、ご苦労様ではなく、「お勤めお疲れ様でした」を使う方がいいでしょう。
出所の時に使う「お勤め」
ここでの「お勤め」は仕事というよりは、義務・任務として捉えると分かりやすいでしょう。
何か犯罪を犯して刑務所に収容された場合、義務として毎日工場などで作業を行います。また、刑務所に入ること自体も犯罪者の「義務」に当たるでしょう。服役後、出所してきた人間に「お勤めお疲れ様です」と声をかけるのはその義務を終えたからです。
また、「お勤めご苦労様です」という台詞の場合もありますが前述したように「ご苦労様」は目上の人に使うのは失礼にあたるので、親分に対して使うのは誤りです。
[no_toc]
敬語での「お勤め」の使い方
意味の項目でありましたが、「お勤め」は「勤め」を丁寧に言った言葉ですので「お」がついて丁寧語にあたります。
尊敬語としての「お勤め」
例として、「どちらに、お勤めしているのですか?」は間違いです。「どちらに、お勤めされているのですか?」は正しい使い方です。
謙譲語としての「お勤め」
例として「わたしは、この会社にお勤めしています」と自分のことを紹介するのは間違っています。「わたしは、この会社に勤めています」が正しい使い方です。
自分や身内には「勤め」の方を使うよう心がけましょう。
「お勤め」の類語
道徳や法律上で義務のある仕事という意味の「お勤め」は「義務」「責任」「役目」「責務」など。料金を得るために行う仕事という意味の「お勤め」は「課題」「職務」「任務」「仕事」など。他の人に対して行う「お勤め」は「サービス」「奉仕」「勤務」「労務」など。
これらが「お勤め」の類語として使われる言葉です。言い換える必要がある際に使ってください。
「お勤め」と「お務め」の違い
つとめ [3] 【務め・勤め】
①
当然しなければならない事。任務。義務。 「国民としての-」
②
会社・官公庁などに雇われて,働くこと。また,そこでの仕事。勤務。 「 -を探す」 「 -に出る」 「 -をやめる」
③
毎日仏前で行う礼拝・読経(どきよう)。勤行(ごんぎよう)。 「朝のお-」
④
遊女の仕事。 「おもへば世に此道の-程かなしきはなし/浮世草子・一代女 1」
⑤
揚げ代の支払い。 「げんなまでさきへお-を渡しておいたから/滑稽本・膝栗毛 初」
「お勤め」と「お務め」は似ている
漢字での使い分けですが「お勤め」は出勤や勤務の「勤」という字を使っているので
「仕事」という意味合いが強く、会社や勤め先に関連するときによく使われます。また、「勤」という漢字は「勤行」の漢字でも使われるので、法事や仏教などに関連するときにもよく使われます。
「お務め」は任務や責務の「務」という漢字を使っているので「役割」という意味合いが強く、議長の務め、親としての務めなど仕事以外での「役」「立場」に関連するときによく使われます。
宗教での「お勤め」の使い方
意味の項目でもあったように、仏教での読経や勤行のことを「お勤め」と言います。お仏壇の前で、お経を読んだり手を合わせたりすることです。
[no_toc]
僧侶がする「お勤め」とは
お坊さんのお勤めは早朝に行われ、無心になってお経を唱え心を整えます。一時期、お寺に泊まるのがブームになりましたが、そういう時はこのお勤めに参加することが可能です。
葬式での「お勤め」の使い方
宗派にもよりますが、枕経(まくらきょう)と言って、故人の方の枕元に小さな祭壇を設けて行うお勤め、お通夜でのお勤め、葬式でのお勤め、火葬の際のお勤め、と計4回行われることが多いです。
「お勤め」という言葉に詳しくなれましたか?
今日もお勤めお疲れ様です。