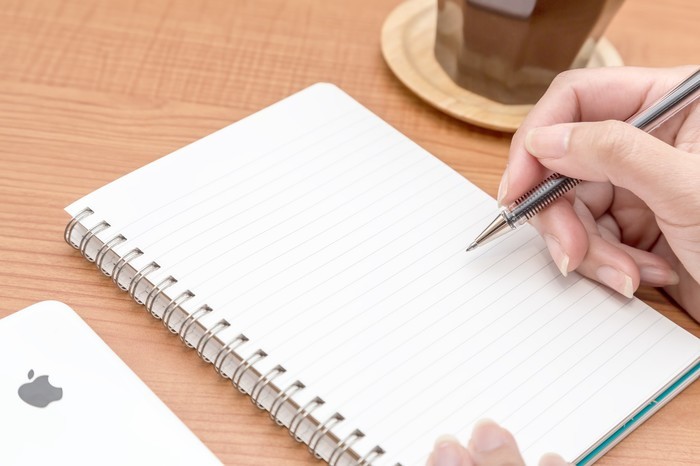[allpage_toc]
「同じ失敗を繰り返さないようにするにはどうしよう?」
「駄目だったことを振り返ることの重要性ってなんだろう?」
こういったお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、振り返りの重要性や書き方、成果を出すためのフレームワークなどをご紹介しています。
この記事を読むことで、振り返りをする際の書き方のポイントや注意点、フレームワークの使い方を理解することができるため、個人でもっと結果を出したり、チームで行うプロジェクトでより大きな成果を求めることができたりするでしょう。
効果的な振り返りの書き方を学ぶことで自分やチームを成長させたい方は、是非チェックしてみてください。
振り返りをする重要性とは?
なぜなら、自分やチームの行動を客観的に理解することによって、次の行動に移る前に改善点を確認することが可能になり、より効果的に行動することができるようになるからです。
たとえば、コールセンターで働く従業員に振り返りを行った際のパフォーマンス測定によると、1日の終わりの15分間でその日の振り返りを行った従業員には、振り返りを行わなかった従業員に比べ10日後には23%のパフォーマンスの向上が見受けられたそうです。
また、振り返りを行うことによって、行動の1つ1つの意味が分かり、自分の癖や細かい改善点が明確になります。
目標に対しパフォーマンスが低い場合に振り返りを行うと、原因と修正すべき点が明確になり、そのうえで行動し、また振り返るというサイクルを回すことによって、効率や生産性の改善が可能になるのです。
そして、改善によって自分の成長が実感できるとモチベーションが向上するため、さらに前向きに行動できるようになります。
したがって、振り返りを行うことは非常に重要と言えます。
振り返りの書き方のポイント
なぜなら、振り返りとは、あらかじめ目標を設定する段階で振り返りをするタイミングやそのときまでに期待する効果を明確にしたうえで、振り返りをおこなったときに期待値とのズレを確認し、次の行動を改善していく取り組みだからです。
つまり、期待値とそれに対する誤差の確認・修正を行っていく作業と言えます。
そのため、振り返りの書き方について、次の3点に気をつけましょう。
継続できる工夫をする
なぜなら、振り返りを継続することで改善点の確認と行動のサイクルを繰り返し、パフォーマンス向上につなげることができるからです。
たとえば、筋力トレーニングでは継続して行うことで自分が持ち上げられる重量が増えたり、体つきが変わったりするとモチベーションが高まりますよね。
つまり、継続し、効果が見えるようになることによって自分の成長を実感したり楽しみを見出し、さらに続けられるようになると言えます。これは振り返りにおいても同様です。
最初は面倒に思ったり、そもそも多忙な中で時間がとれないことも考えられますので、1日10~15分程度、どこかのタイミングでレポート作成をしたり日報を書いたりする時間をつくる工夫をすることをおすすめします。
この場合、あらかじめスケジュールの中で振り返りを行う時間を決める、通勤・通学の時間を充てる、就寝前に時間をつくる、といったスキマ時間の活用が有効です。
成果が明確になるよう定量的かつ具体的に書く
なぜなら、定量的な書き方をすることで事実や具体的な成果が明確になり、自分や第三者が適切に評価できるようになるからです。
たとえば、「積極的なセールスを行い、売上がアップしました」という書き方では、どんなセールス活動をどのくらい行い、いつの時点と比べてどの程度売り上げが上がったのかが分かりませんよね。
そこで、「テレアポを20件行い、2件アポイントを取得できたため、売上が前月対比10%アップしました」という書き方にすると、活動内容もはっきりとし、効果も非常に分かりやすくなります。
そのため、今後の活動について、テレアポの件数を増やすのか、アポイントがもっと効率よくとれるようテレアポの内容を見直しするのか、といった改善に向けた次の行動が見えてきます。
したがって、振り返りの書き方においては、定量的かつ具体的に書くことが大切です。
感想文・反省文とならないよう注意する
なぜなら、振り返りに必要なのは事実や原因に対する分析や自分の意見、考察であり、上司やチームの他のメンバーは自分の分析結果や意見、考察を共有し、改善点があればフィードバックすることになるからです。
たとえば、「予想以上に大変でした」「成約につなげることができず残念でした」という書き方ではただの感想文であり、なぜ大変だったのか、次はどうしようと考えているのかが見えてきません。
そこで、「○○という点に予想以上に時間がかかったため、次回は△△という点に留意して対応します」「成約につなげることができませんでした。その理由は□□でしたので、次は◇◇というアプローチをしてみようと思います」という書き方であれば、原因がどのようなところにあるのか、改善に向けた取り組みが正当かを評価できますね。
したがって、単なる感想文・反省文のような書き方にならないよう、事実や原因の分析や自分の意見、考察を書くことが大切です。
なお、慣れないうちは書き方のテンプレートを事前につくっておいた方がいいでしょう。
振り返りの基本理論
そこで、ここでは具体的な手法の前に、まずは振り返りの基本理論を3点ご紹介します。
ダブルループ学習
たとえば、シューズメーカーのビジネスマンが結果の振り返りの際、もっと靴を売るために自分や自社が行っている靴の売り方を見直しするのと、そもそも売る前提となっている市場自体を見直しするのかでは大きく話が変わりますよね。
市場自体を見直しすることで、たとえば、まだ靴を履く文化がない未開の地に販売する戦略を立てるというアクションが選択肢に入ってきます。
ちなみに、結果から行動を見直すことを繰り返し行う行為をシングルループ学習と言います過去の学習や成功体験から得た考え方に基づいて改善を繰り返すという理論です。
これに対し、ダブルループ学習は、行動の基になっている前提から見直しをすることによって、過去の学習や成功体験を捨て、よりイノベーティブなアクションを促すための理論と言えます。
特に、ゲームチェンジが激しい昨今では、エネルギーがガソリンから電気・水素にシフトしつつあるように、前提条件自体が変わることもあるため、シングルループ学習では十分に対応できないことも考えられ、ダブルループ学習によってイノベーションを起こすことが必要です。
ジョハリの窓
この理論は、サンフランシスコ州立大学の心理学者であるジョセフ・ルフトとハリ・インガムが、「対人関係における気づきのグラフモデル」として発表したもので、のちに2人の名前を組み合わせた「ジョハリの窓」とう呼称がつきました。
「窓」という名前のとおり、自己の特徴を4つの窓に区切り、自己認識と他者認識の違いを明確にするものです。
4つの窓とは、自分も他人も知っている自己を表す「開放の窓」、自分は気がついていないが、他人は知っている自己を表す「盲点の窓」、自分は知っているが、他人は気づいていない自己を表す「秘密の窓」、誰からもまだ知られていない自己を表す「未知の窓」の4つです。
なぜジョハリの窓が振り返りで有効かというと、客観的に見た自分の特徴を理解し、他人の認識とのズレを修正していくことによって、コミュニケーションを円滑にすることが期待できるからです。
たとえば、今まで誰にも話していなかった自分の考えを他者に話した際に、思った以上に共感されたり驚かれたりすることによって、より深い話ができるようになることがありますね。
つまり、自己開示をしていくことによって、ジョハリの窓でいう「秘密の窓」を開放し、より積極的な意見交換ができる人間関係を築くことで、より質の高い商品やサービスを生み出すことを可能にするのです。
[no_toc]
経験学習モデル
この理論は、具体的経験、内省、概念化・抽象化、実践の4つのステップで成り立っています。
具体的経験とは、初めての分野や業務に取り組んでみることです。
その中で大切なのは、単にマニュアルに沿って対応するのではなく、なぜマニュアルがそのような内容になっているのか、なぜ上司からその内容の指示が出たのかを考え、自分はどうすべきだったのか、といった、自分の考えやプロセスについて考察することです。
なぜなら、それによって次の内省がより有効になるからです。
内省とは、行動と結果について振り返りを行うことです。
その際、プロセスについて考えることが重要で、特にうまく結果に結びつかなかった場合、どの判断によってうまくいかなかったのか、ほかにどのような判断材料があればうまくいったのかを考えることによって、次のアクションにつなげやすくなります。
概念化・抽象化とは、具体的経験と内省から得た気づきをほかのことにも応用できるように言語化することです。
概念化・抽象化するためには、紙に書きだして頭の中を整理すること、自分だけでなくチームのほかのメンバーにも理解できるレベルで落とし込むことが大切です。なぜなら、チーム全体で学びを共有することによって、組織力の向上につながるからです。
実践とは、概念化・抽象化して得られた気づきを実際に試してみることです。
概念化・抽象化した段階ではまだ仮説にすぎないため、実際の現場で試行し、さらなる改善点や課題を抽出します。
実践で大切なのは、着手するまでの時間を短くし、素早く取り組むことです。なぜなら、素早く実践することによって新たな具体的経験が得られ、経験学習モデルのサイクルを早く回せるようになることで、ビジネスのような早い変化が求められる現場にも対応できるようになるからです。
振り返りの適切な書き方につながる具体的手法
ここでご紹介するフレームワークを使うことによって、的確に原因と課題を発見するために活用することができます。なぜなら、どのような振り返りの書き方をすればいいか分からない状態で検証を行うと、本質から外れた部分に原因と課題を見出してしまい、よりよい改善にはつながりにくいからです。
したがって、正しい振り返りの書き方できちんと改善効果が得られるよう、書き方の具体的なフレームワークを4つ確認しましょう。
KPT(Keep・Problem・Try)
言い換えると、うまくいっていることと直したいことをそれぞれ確認し、どうやって解決し改善するかを考えるための書き方と言えます。
KPTの具体例・効果
まずは、紙・ホワイトボードなどに大きく四角形を書いたうえで、「Keep」「Problem」「Try」の箱をつくり、「Keep」から順に記入しましょう。色付きのペンや付箋を使うと後で整理しやすくなります。
書き方の順番は、最初に「Keep」の欄から入りましょう。なぜなら、「成果がでており継続すること」、つまり、「よかったこと」から振り返ることになるからで、その後の項目についてもポジティブな気持ちで取り組みやすくなります。
つぎに、「Problem」の欄を同様に書きだしましょう。このとき、先ほどの「Keep」とは違う色のペンや付箋を使用すると見やすくなります。
さらに、「Try」の欄に「Keep」「Problem」を踏まえて、新たに実践することや問題に対する解決策、やるべきこととやめるべきことを整理しましょう。
KPTを用いることで、たとえば、ホワイトボードにチーム全員で課題を書き出し、それを解決するための方法を一緒に考えるという構図になるため、メンバーそれぞれの認識を可視化したうえで客観的に分析することができ、チームの一体感をもってに次のアクションを検討することが可能になります。
PDCA(Plan・Do・Check・Act)
まず、「Plan」で、5W1Hに沿って、いつ、どこで、だれが、何を、どうして、どのように行うのかを検討します。
つぎに、「Do」では「Plan」で策定した計画を実行します。その際、計画した内容や方針に従うこと、結果を数値化することがポイントです。
「Do」の後は「Check」により、行動した結果を振り返りましょう。ここでは客観的に問題点や課題を検証することが大切なので、データ・数値に注目し判断することが必要です。
最後に、「Act」で「Check」によって見えた課題について考え、改善するためのアクションを起こします。
そして、以上の4つのプロセスを繰り返していくことで次の業務を円滑にするのです。
PDCAの具体例・効果
たとえば、顧客の訪問件数を何件にするのか、効果的な面談にするためにいつ訪問するのか、どのような活動がどのくらいの効果をもたらしたのか、といった点を具体的な数値や計画に落とし込んだ書き方によって、改善策が明確になるため、より効果的にPDCAを回していくことができます。
ちなみに、PDCAの活用で有名なのがトヨタ自動車です。トヨタ自動車では、「5W1H」を使っているのが特徴なのですが、「5W1H」の「5W」は「なぜを5回繰り返すこと」であり、最後に「How:どうやって」を考えることによって、3M(ムリ・ムダ・ムラ)をなくし、効率的な生産を可能にしているのです。
つまり、PDCAを効果的に回す書き方とは、定量的に計画を立てて検証すること、「5W1H」を使って具体的に考えることが大切だと言えるでしょう。
YWT(やったこと・分かったこと・次にやること)
先にご紹介したPDCAより経験を重視した理論であり、行動はするけれど振り返りをしない、あるいは振り返りはするものの次の行動に活かされていないような場合に、YWTを活用することによって改善に向けた気づきを確認し、次の行動につなげることができるようになります。
YWTの具体例・効果
まずは、「Y:やったこと」を書き出しましょう。たとえば、セミナーの開催に向けた集客のように、取り組んだことについて思い返します。慣れないうちは思いつくままにとりあえず書き出せば大丈夫です。
つぎに、「W:分かったこと」を確認しましょう。たとえば、集客を図ったけれども参加者が集まらなかった、といった具合に、経験を通じて学んだことを書きましょう。注意点としては、「Y」と同じような事実だけを拾うのではなく、「Y」からの気づきを抽出するということです。
最後に、「T:次にやること」を検討します。たとえば、集客のための告知の方法やタイミング、参加者がアクセスしやすい会場選び、などです。「W」を踏まえた改善策についてメンバーで意見を出し合いましょう。
YWTについてもプロセスを繰り返すことが大切です。特に、「W」に基づく「T」を考え、次の「Y」につなげていくことを継続しましょう。
4行日記
「事実」は、その日にあった客観的な事実、「発見」は事実からの気づき、「教訓」は「発見」からの学び、「宣言」は将来の自分のありたい姿に向けた次のアクションです。
上記の4項目を4行で振り返り、気づいたことや次につなげることを検証します。
書き方は、1行あたり20文字、合計80文字程度でまとめるというシンプルなものです。
短い文章でまとめることから、課題発見力や問題解決力だけでなく、表現力や論理的思考力も育む効果が期待できます。
4行日記の具体例・効果
[no_toc]
まず、「事実」はその日あった出来事の中で印象に残っていることについて書きましょう。たとえば、行動が気になっていた人に問いかけをした、というように、1つの出来事を短く書きます。
「事実」に書くことは自分の関心や優先順位の高いものになる傾向があるため、「事実」を書き出すだけで自分の癖や考え方を確認することができます。
つぎに、「発見」は事実に対して自分がどのように考えるのかを記します。たとえば、相手の行動の理由が分かり、対応方法が見えた、のように、得られた気づきに対する直感的な書き方にしましょう。
さらに、「教訓」では自分が学んだことを書きます。たとえば、問いかけによって解決方法が見えることがある、といった書き方で、学んだことを抽象化しましょう。
最後に、「宣言」では自分がありたい姿について、現在進行形で「なっている」と言い切る書き方にしましょう。なぜなら、潜在意識下ですでにありたい姿になっていると描くことによって、目標に近づくことができるからです。
たとえば、対人関係の問題を解決することができている、といったに書き方をすることによって、潜在意識の中でありたい姿を達成できているイメージを構築しましょう。
振り返り類語と相違点
ここからは、振り返りの類語を3つご紹介します。それぞれの内容と相違点について確認しましょう。
リフレクション(内省)
振り返りとリフレクションの違いは過去の行動を振り返るときの立ち位置で、主観を交えず、より客観的な目線から見つめ直すのがリフレクションです。
反省
振り返りと反省の違いは、確認するときの対象で、反省が失敗や間違った考え方に対して行うのに対し、振り返りは成功からも失敗からも気づきを発見します。
また、反省では責任の所在がどこにあったのかを確認するケースもありますが、振り返りは責任の追及はせず、より良い結果を出すために行います。
感想
振り返りと感想の違いは、次の行動につながる改善策が含まれているかどうかです。
たとえば、「いい結果が出なくて残念だった」「あれだけやったのにうまくいかず悲しかった」は感想で、自分の思ったことや感じたことをまとめて終わっていますが、「成約になったのが1件だけだったため、次は商談件数を増やすためにテレアポの件数を10件増やそう」は振り返りで、次につながる改善策まで考えています。
したがって、振り返りの方がより良い結果を出すにはどうすればいいかを検討する思考であると言えます。
振り返りができる人・できない人の違い
ここでは、それぞれの思考の特徴をご紹介します。
振り返りができる人の特徴
なぜなら、自分のことを常に客観的に見る人は、自分が置かれた状況で求められる期待値や現状とのギャップを考えることで、今何が足りないのか、どうすれば求められる水準に届くのかを見据えているからです。
たとえば、本来自分に期待されているのはどのような成果なのか、期待値に対して現状はどの程度離れているのか、現状と期待値の差を埋めるにはどうすればいいのか、といったことを常に考えています。
そのため、振り返りができる人とは常に自分のことを客観視し、現状に対する改善策を考え続けている人であると言えます。
振り返りができない人の特徴
なぜなら、うまくいかない原因を見つめ直すことがなく、言い訳や失敗に対する責任の所在ばかりに気を取られてしまい、次はどうすればうまくいくのかを検証しないからです。
たとえば、失敗やトラブルの責任が誰にあるのか、起こった事象に対し自分は悪くないと常に考えており、一時的な謝罪をするだけで終わってしまい次の改善には向かいません。
したがって、振り返りができない人とは、考えが現状で終始してしまい、未来に向かいにくい人であると言えます。
振り返りの書き方をマスターして次回につながる取組みをしよう
そのためには、まず振り返りの書き方を習得する必要があります。
フレームワークを使い、継続的にサイクルを回すことによって、次回につながる取組みをしましょう。
改善点を検証し、実践することによって、自分やチームの成長が実感できるようになり、より良い結果を出すことができるようになるでしょう。