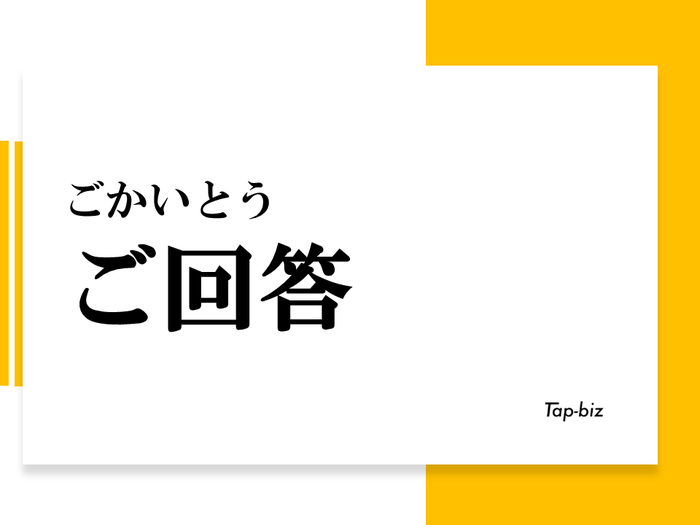[allpage_toc]
「『ご回答』ってよく聞く言葉だけど、どうやって使えばいいの?」
「『ご回答』を別の言い方にしたいときはなんて言えばいいかな?」
「ご回答」という言葉の正確な意味をご存知でしょうか。ビジネスシーンなどで見聞きする人は多いのではないでしょうか。
この記事では、「ご回答」の意味や使い方などについてくわしく解説しています。
記事を読むことで、「ご回答」の意味をはじめ、使い方や使う際の注意点、また言い換え表現、謙譲表現、尊敬表現を知ることができます。また、英語表現についても解説していますので参考にしてください。
ビジネスシーンで今より活躍するためにどうぞお役立てください。
「ご回答」の意味
この「回答」に接頭語の「ご」をつけると「ご回答」という敬語になり、尊敬の意味をもつようになります。
「ご回答」の使い方・例文
自分で回答する場合
では、どんな言葉をあとに続ければよいのでしょうか。
結論からいうと、「ご回答」のあとに続く正しい言葉は「申し上げます」です。「ご回答」自体が敬語のため、あとの言葉はどんな言葉でもよい気がしますが、「ご回答申し上げます」とすることでより丁寧な言い方にすることができます。
相手に回答を求める場合
また、より相手に敬意をあらわす場合には、「ご回答をよろしくお願いします」や「ご回答をお願い申し上げます」とすると、より丁寧な印象が与えられるでしょう。これは対面の場合だけではなく、メールを打つ際にも使うことができます。
このように、相手に対して何かしらの行動を求める場合は、「お願い」という言葉をあとに続けるのが適切です。
「ご回答」を使う際の注意点
そこでここからは、「ご回答」を使う際の注意点についてまとめていきます。
使い方に注意して、自分の考えを相手に正しく伝えられるようにしましょう。
「お回答」とは使わない
ただし、漢語にはすべて「ご」をつけるわけではなく、例外は存在します。例えば漢語でも「食事」を「ご食事」とはいいません。また、「返事」のように「ご」と「お」のどちらでも使える場合も存在します。
後ろに続く言葉で意味合いが変わる
あとに続く言葉によって意味が変化するのが敬語の特徴ですが、「ご回答」はその典型的な例に当たります。
[no_toc]
間違いやすい使い方を把握しておく
ここからは、よくみられる間違いやすい使い方を紹介していきますので、「ご回答」を使うときの参考にしてみてください。
「ご回答ください」
このような言い方では、相手が目上の方や立場が上の方の場合に「ご回答」という言葉を使っていても敬意を示している言葉だと受けとってはもらえず、正しい意図が伝わらない可能性が高いです。
やはり相手に回答を求める場合には、「ご回答お願いいたします」と伝えた方がより敬意が伝わりやすいでしょう。
「ご回答いたします」
一見すると正しい敬語の使い方に感じる人が多いと思いますが、「回答」という名詞に対して「いたします」という尊敬語を使うのは正しくなく、敬語としては認められていません。
相手に対して「回答します」と伝えたい場合には「お答えいたします」を使った方が自然であり、自分の気持ちが正しく伝わります。
「ご回答させていただく」
さらに、「させていただく」は本来、相手から許可を受けて使う言葉ですので、「ご回答させていただきます」と相手の許可を得ずに一方的に宣言するのは不適切になってしまいます。
この表現はビジネスシーンでよく使われていますが、本来は間違った表現なので使用は避けた方がいいでしょう。正しく伝えたい場合は「質問させていただく」を使いましょう。
「ご回答」の言い換え表現
ここからはいくつかの言い換え表現について紹介します。
「ご返答」
「返答」は「問いに答えること」や「呼ばれたときの受け答え」を意味し、相手からの行動を受けて、それに返事をすることをあらわします。
敬語の種類は文脈によって尊敬語・謙譲語・丁寧語のどれにでもなりえます。相手が答えを返すときは「尊敬語」、自分が答えを返すときは「謙譲語」、ただ「回答」を丁寧に言うだけなら「丁寧語」です。
「ご解答」
「解答」の意味は「問題を解いて答えを出すこと、また、その答え」です。「解」という漢字のとおり、試験や問題を「解いて」、「答え」を出すというニュアンスになります。
「回答」と同じような「返事」という意味ではなく、謎解きをして答えを導き出すという意味なので、混同しないようにしましょう。
英語であらわすならば、「回答」は「レスポンス」で、「解答」は「アンサー」と覚えておくと分かりやすいでしょう。
「ご回答」の謙譲表現
ここからは謙譲語として用いる場合の使い方をみていきます。
[no_toc]
「ご回答申し上げます」
「申し上げる」はかしこまった場面でも用いることができるフレーズで、丁寧な印象を相手に与えることができます。
文章で使用する場合、「申し上げる」と「申しあげる」のどちらを使えばいいか迷う方も多いと思います。これについては、動詞として使用する場合には漢字表記にして、補助動詞として使用する場合はひらがな表記にするという決まりがあります。
したがって、「ご回答申し上げる」の場合は漢字で表記するのが適切です。
「ご回答差し上げる」
一見すると謙譲語の「ご」と「差し上げる」がついているので、二重敬語だと思ってしまいます。しかし、二重敬語はひとつの語に対して同じ種類の敬語を使ってしまうことです。この場合は「ご」は「回答」についていて、「差し上げる」は「与える」の謙譲語として別々で使っているので、問題ありません。
ただし、「差し上げる」はもともとの言葉が「与える」のため、「回答してあげる」と上から目線に聞こえしまうことがあります。「ご回答申し上げます」などの丁寧な表現で伝えた方がよいでしょう。
「ご回答がございます」
「ご回答がございます」は「ご回答」と「ござる」と「ます」から成り立っています。「ご回答」は謙譲語、「ござる」は「ある」の丁重語、「ます」は丁寧語のため、二重敬語ではありません。
「ご回答があります」は似たような表現ですが、「ご回答がございます」の方が自然に相手に伝えることができます。「あります」を使いたい場合は「回答があります」とした方がすっきりした印象になります。
「ご回答」の尊敬表現
ここからは、「ご回答」の尊敬表現について紹介していきます。
「ご回答ありがとうございます」
回答してもらった際には、答えてくれた相手に対しお礼の気持ちを伝えることがとても大切です。ビジネスシーンでも、取引先の人などに質問したりする場面は多いので、「ご回答いただきありがとうございます」というお礼の気持ちを伝えるようにしましょう。
「ご回答お待ちしております」
この場合の回答につく「ご」は尊敬語であり、「お待ちしております」の「お」は待っているのが自分のため謙譲語となります。また、「おります」は「いる」の丁重語である「おる」に、丁寧語の「ます」をつけています。
「お待ちしております」は単純に「待っている」というよりも、「願っている」という意味合いが強い言葉になります。
この表現は目上の人に「回答してほしい」とお願いする場合に使います。催促していると思われないためにも、「ご回答お待ちしております」などの柔らかい言葉で伝えた方が失礼がありません。
「ご回答いただく」
「ご回答」の「ご」も、相手が回答するので尊敬語です。また、「いただく」は「もらう」の謙譲語になります。謙譲語を使用することで自分をへりくだり、相手に敬意を示す表現になります。
「ご回答いただけますと幸いです」とすると、より丁寧になります。
「ご回答の程」
回答をするのは相手なので、接頭語の「ご」は尊敬語です。また、「の程」は「~してもらうよう」「~してくれるよう」という意味があります。
「ご回答願います」や「ご回答ください」は一方的に要望・要求するようなニュアンスになってしまいますが、「ご回答の程」とすることで断定を避け、柔らかい表現で伝えることができます。
「ご回答」の英語表現
[no_toc]
「回答」の意味で使いたい場合は「response」となります。また、堅い語だと「reply」も使うことができます。
まとめ
「ご回答」という言葉はビジネスシーンにおいてよく使われる言葉です。しかし、実は間違って使っていることが多い注意すべき表現でもあります。
場面に応じた使い方や意味について理解し、充実したビジネスライフを送っていただければ幸いです。