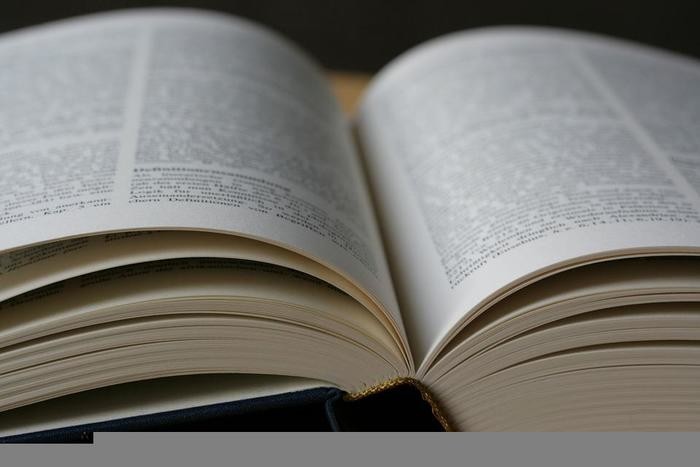[allpage_toc]
「尊敬語や謙譲語があった気がするけど、どう使うんだっけ?」
「行くや言うなどのよく使う言葉の使い方も知りたい」
このように謙譲語などの正しい敬語の使い方を知りたいと思っていても、何となく雰囲気で使っているという人もいるのではないでしょうか。
ここでは、敬語の分類や「する」の謙譲語の使い方、他の動詞の謙譲語など例文とともにを紹介しています。
この記事を読むことで、「する」の謙譲語や似た意味の「させていただく」と使う場合の注意点などを知ることができます。その知識をもとに、自分の伝えたい内容を正しい謙譲語を使って伝えることができるようになるでしょう。
目上の人との会話や仕事などの場で違和感のない言葉遣いをしたい人は、ぜひこの記事をチェックしてみてください。
敬語について
尊敬語、謙譲語、丁寧語があり、それぞれどのような場面で使うことが望ましいか決まっているのです。
上下関係に限らず、相手を尊重し不快な思いをさせないためにも正しい敬語を使えるようにしておくと良いでしょう。
対面で敬語を使う際には態度にも注意して、失礼のないように気を付けてください。
尊敬語
尊敬語の中でも「くださる」「いらっしゃる」など動詞が変化するパターンと「あなた」「御社」など名詞が変化するパターン、「お元気」など形容詞が変化するパターンがあります。
謙譲語
謙譲語は目上の人や取引先またはお客様に対して用いることが正しく、目下の人や同等の立場にある人には使いません。
「伺う」「お届けする」「いたす」などがあり、文章に合わせて違和感のないよう使い分けができると良いでしょう。
丁寧語
「する」を丁寧語で表すと「します」になり、文にすると「お電話します」などと表現することができます。日常的にもよく用いられる言葉遣いで、聞いた側としても使う側としても、気持ち的に堅くならない言い方でしょう。
目上の相手でも同等の相手でも使える点が重宝します。丁寧語で話すことを心がけると、最低限の敬語は使えると考えてもらえるでしょう。
「する」の謙譲語とは
現代では「いたす」という言葉をそのまま使うことはなかなかありませんが、「です・ます」の言葉を付け加えて使うと問題ないでしょう。
言い方は状況によって変えますが、目上の人や取引先・お客様などに対して「する」ことを示したい時は「いたします」を用いると良いです。
「いたす」の使い方
立場に関係なく、自分以外の誰かが「する」ことを「いたす」とは言わないように気をつけましょう。しかし場合によっては会社内の誰かがすることを「いたす」と表現することがあります。
たとえば、自分ではなく会社内の佐藤というものが説明すると伝えたいときは「佐藤がご説明いたします」と表現しましょう。自分の所属する会社を低く表現すると考えることができます。
「させていただく」の使い方
「手荷物を調べさせていただきます」「休ませていただきます」「述べさせていただきます」などがあります。
似た表現で使い方をよく間違われる言葉は「拝見させていただきます」です。この文は二重敬語になっているため、敬語としては正しい使い方ではありません。
「する」の謙譲語を使う場面と例文
「翌日のお昼頃に、お電話をいたします。」
こちらを謙譲語を使わないで言うと「お電話をします」という表現になり、丁寧な言葉遣い全般を省くと「明日の昼に電話をかける」といった意味になります。
電話の次は、メールで返信する際の「いたす」です。「順次お返事を致しております。」という自動返信メールの言葉を見かけたこともあるでしょう。この文では「あなたのメール内容を確認したら返事をする」という意味があります。
[no_toc]
主な動詞の謙譲語と例文について紹介
正しい敬語を覚え相手への敬意を表現できるようになると、仕事の場などで活躍できる場面も増えるでしょう。
「来る」の謙譲語と例文
「参る」は「参りました」という勝負事の際に使う表現もあります。そのため伝えたい内容をしっかり考えてから使うように気をつけましょう。
「いる」の謙譲語と例文
「お世話になっております」「担当の者は不在にしております」など聞いたことがあるものもあるでしょう。相手の立場が上の場合には「社長はおりますか」などとは言わず「いらっしゃいますか」と使うことに注意します。
「行く」の謙譲語と例文
話を聞いてもらう相手に対して使う場合は「御社に参ります」、行く先の相手に敬意を払うときに使う場合には「御社に伺います」となります。
「行かせていただきます」という言葉も耳にしたことがあるかもしれませんが、謙譲語ではなく誤った使い方となりますので使わないよう気を付けましょう。
「言う」の謙譲語と例文
「弊社の鈴木が申しておりました」と使う場合、鈴木さんが会社の上司であっても自分の所属する会社のことをへりくだって表現することが正しいとされるため、文章として適切な表現といえます。
主な謙譲語を覚えて相手に丁寧な印象を与えよう
使っていくうちに使い分けなどもできるようになっていきますので、最初は間違えながらでも違和感なく使えることを目指しましょう。