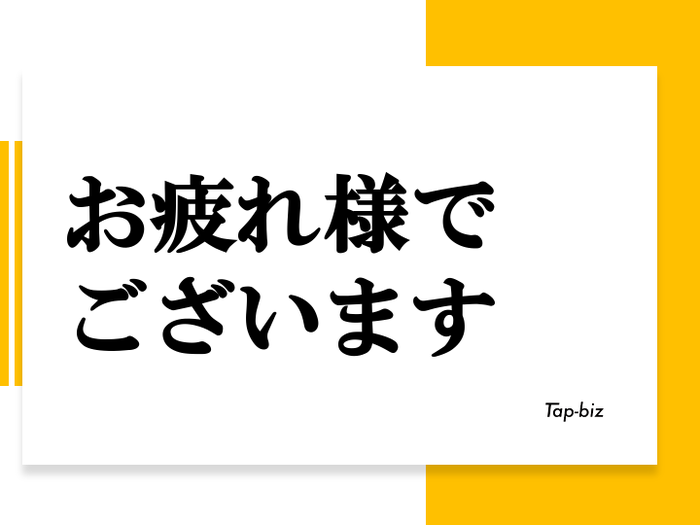[allpage_toc]
では「お疲れ様でございます」はどうでしょうか。「お疲れ様でございます?お疲れ様ですじゃだめなの?違いは何?」と思われた方もいると思います。
そこで、今回は「お疲れ様でございます」という敬語について使い方や例文、他の言葉に言い換えるなら?など、詳しく掘り下げ、解説していきます。
敬語の正しい使い方は社会人として身につけたいものですが、何年たっても、自信を持って使いこなせていると言い切れる人は意外に少ないのではないでしょうか。
これを読めば、「お疲れ様でございます」の正しい使い方を知ることができます。ぜひ、お仕事にお役立てください。
「お疲れ様でございます」の意味
まず「お疲れ様」のみに着目します。「お疲れ様」とは相手の労苦をねぎらう際に用いる言葉です。元々はねぎらうことは目上の人が目下の人に行うものとされていました。
しかし、時代は変化し「お疲れ様」という表現を目上の人や同僚に述べることが間違いではないということを会社の研修で学ぶこともあります。また、「お疲れ様」を挨拶として使用していることが増えています。
さらに語尾に「ございます」という敬語表現をつけることにより、より丁寧な表現になります。
「お疲れ様でございます」の使い方・例文
ビジネスシーンの場合
ただ、同僚に「お疲れ様でございます」という非常に丁寧な敬語を使うことはありません。寧ろ使用する相手が間違っていると言えます。使い方を間違うとねぎらいの言葉も無駄になってしまうので注意しましょう。
つまり、「お疲れ様でございます」は上司に使用することがわかります。しかし、「お疲れ様でございます」は敬語ではあるけれど、あまりにも丁寧すぎる表現なので違和感を覚える人もいます。使い方には注意が必要です。
「お疲れ様でございます」という敬語の例文をいくつか挙げてみます。使い方はケースバイケースです。「お疲れ様」と使い方は同じなのですが、前提として普段から敬語を使用する間柄の人に使用します。
- 「本日は大変お疲れ様でございました。」
- 「お疲れ様でございました。お先に失礼させていただきます。」
- (服の試着が終わり)「お疲れ様でございました。」(お客様に対して)
メールの場合
まず、一般的に社内でのメールにおいて、冒頭の書き出しの部分で定型文として使われているのは、「お疲れ様です」になります。
「お疲れ様でございます」が「お疲れ様です」をより丁寧にした敬語である、ということから、「お疲れ様でございます」をメールで使うのは社内メールで、上司など目上の人とやり取りする場合になります。
ただし、メールを送る時間帯によっては「おはようございます」など他の言葉に変える方が良い場合もありますので、臨機応変な対応が必要です。
「お疲れ様でございます」の注意点
もちろん、社長のような立場の人に対して使っても、現代の考えでは使っても問題はありません。
しかし、元々の「お疲れ様」という言葉は「目上の人が目下の人に使うものだ」、という考えを今でも持っている人にとっては失礼になります。使うときは注意するようにしましょう。
その他、気をつけた方がいい注意点を挙げてみました。
[no_toc]
午前中には使わない
失礼とまではなりませんが、午前中までは「おはようございます」を使う方が良いとされます。
そこまで気にせず、習慣で「お疲れ様です」「お疲れ様でございます」を使ってしまう人が多いと思いますが、こういったことまで気を配るようにすると、できる人という印象を与えることができます。
ビジネスシーンでは社外には使わない
では、代わりにどんな敬語を使えばよいのでしょうか。
それは「お世話になっております」です。電話や、訪問する際でも感謝の意もこめた一言として使うことができます。
葬儀の場面では使わない
そもそも労働をしている場ではないから当然です。まずは仏教の場合でしたら「ご愁傷様です」とお声がけしましょう。
気遣いの言葉をかけるのであれば、「あまりご無理をされてお疲れが出ませんように」などの声かけが適切です。
二重敬語ではない
結論から言いますと、二重敬語ではありません。
「お疲れ様でございます」は、「お疲れ」という名詞+助詞「で」+「ございます」、という丁寧語の組み合わせです。
「ございます」は丁寧語の「です」をより丁寧にしたものであり、二重敬語ではないということになります。
「お疲れ様でございます」の言い換え表現
次に、「お疲れ様でございます」の代わりに使える敬語を考えてみましょう。時と場合によって変わりますが、以下のような言葉が考えられます。
「おはようございます」
社内の人にメールを送る場合「お疲れ様です」や「お疲れ様でございます」は一種のテンプレートになっており、間違っているとか、失礼にあたるということではありません。
午前中という時間帯は、仕事を開始して間もないのでまだ疲れてはいないだろう、ということで朝の挨拶である「おはようございます」を使うのが自然です。
メールにおいてはもちろん、実際に会ってあいさつする場合でも同様です。
「ご足労おかけしました」
社内で使うのであれば「お疲れ様でした」や「お疲れ様でございました」とするところですが、社外の人にいたわりの気持ちを伝えたい時に使える表現です。
いわゆる「クッション言葉」(円滑にコミュニケーションを進めるために使われる言葉)の一つとして、主にメールや電話において使われます。
顧客など社外の人にも使える敬語で、相手に出向いてもらった場合などは、後日「先日はご足労おかけしました」のような言葉を添えてお礼のメールをするとよいでしょう。
「お帰りなさいませ」
「お帰りなさいませ」は、「お帰りなさい」に「ませ」という語句を丁寧に、また上品にするはたらきがある言葉を組み合わせたもので、「お帰りなさい」を丁寧に表現したものとなります。
したがって、上司など目上の人に「お帰りなさいませ」と言うのは間違いではありません。
その上司との関係性にもよりますが、「お帰りなさいませ」に続けて「お疲れ様でございます」と言ってもよいでしょう。
「お世話様です」
良く似た言葉に「お世話になっております」がありますが、違いはどこにあるのでしょうか。
「お世話様です」は、お世話してくれた人に対してお礼をする言葉ではあるのですが、実は敬語ではないので、ビジネス上で使うのは避けます。
「お世話」に「様」「です」をつけ丁寧な表現にはしているのですが、尊敬の意味は込められていないからです。ビジネスシーンでは基本的に敬語である「お世話になっております」を使います。
「お世話様です」は、例えば荷物を配達してくれる業者の人や、部下や同僚など、フランクな関係の人に「ありがとう」の意味もある挨拶をする場面で使います。
「お疲れ様です。お世話様です」と続けて言うパターンもあります。
「失礼いたします」
[no_toc]
ビジネスシーンで「失礼いたします」となると「その場を離れる」ということに断りを入れる、となり「退社する」時の挨拶として使われたり、誰かがいる部屋に入りたい時の断り言葉に使われます。
自分が先に退社する場合、残っている同僚や上司に対して「お先に失礼します」と声をかけます。この時、「お疲れ様です」や「お疲れ様でございます」を先に退社する側が言うのは間違いです。
その時の返答として使われるのが「お疲れ様でした」や「お疲れさまでございました」となります。「疲れられたことでしょう」という相手をねぎらう意味で使われます。
「お疲れ様でございます」は英語で表現できるのか?
しかし、「よくやった」という意味で、ねぎらいの言葉としては「Good Job!」や「Well-done!」がそれにあたります。ただしこちらは同僚や、目上の人が部下などに言う言葉であって目上の人には使いません。
相手の仕事ぶりに感謝したいときは「I appreciate the great job you did」や「Thank you for your hard work」などを使うとよいでしょう。
敬語「お疲れ様でございます」の使い方を理解して適切な場面で使おう
「お疲れ様です」が多用される現在、さらに丁寧な敬語である「お疲れ様でございます」を
使う機会は少ないかもしれませんが、相手との関係性や場面などを考慮して、うまく使い分けましょう。