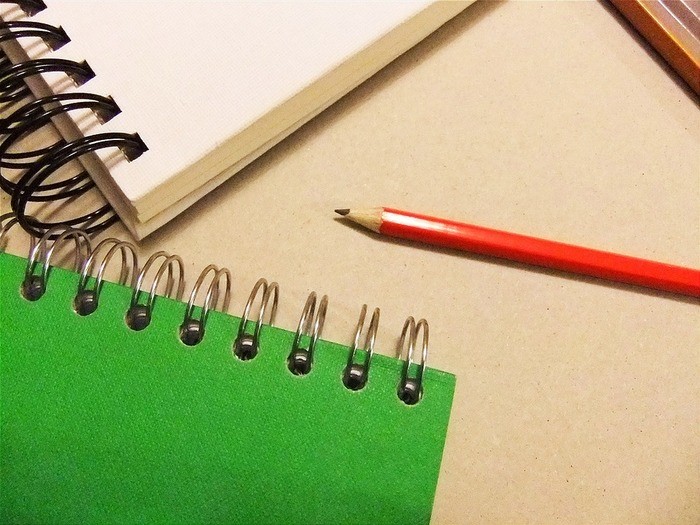[allpage_toc]
「ポートフォリオを作成する際に役立つツールってあるのかな?」
このように、就活を控える新卒生の方はポートフォリオに関する疑問や不安がたくさんあるのではないでしょうか。
この記事では、ポートフォリオの種類や内容といった基礎知識に加えて、ポートフォリオ作成時に注意するポイントや面接官に好印象を与えるレイアウトをご紹介します。
本記事を読むことで、新卒生が押さえたいポートフォリオの書き方や作成時に役立つツールを把握できます。それらの知識をもとに、選考を突破できるポートフォリオを作れるようになるため、就活に不安を感じている新卒生もスムーズに取り組むことができるでしょう。
ポートフォリオの作成に行き詰っている新卒生の方は、ぜひチェックしてみてください。
新卒生が用意するポートフォリオってどんなもの?
企業への自己アピールや履歴書代わりになり、自身の能力やスキルを余すことなく伝えられるため、面接時には採用基準の1つとして評価されます。
口頭で上手く伝えられない場合に有効であることから、言語化が苦手と感じている新卒生にはポートフォリオ作りに注力すると良いでしょう。
ポートフォリオの種類
志望する業界や業種によって求められる形式が変わるため、紙媒体とデジタル媒体の両方を作成しておくと良いでしょう。ポートフォリオはすぐに作成できないことから、予め準備しておくことが肝要です。
ここでは、ポートフォリオの種類をそれぞれ紹介していきます。
紙媒体
紙媒体のポートフォリオの場合、面接時に口頭で説明する場合が多いことから、わかりにくい構成であれば伝えきれないケースがあります。クリアファイルにまとめたり冊子にしたりすることで、情報が伝わりやすくなるでしょう。
なお、冊子にすると紙の材質やサイズなどで他者との差別化が図りやすいため、印象に残るポートフォリオに仕上がります。
Web媒体
特にWebデザイナーの企業は、応募者のコーティングやプログラミングなどのスキルを把握するため、Webポートフォリオを義務付けているケースが見受けられます。Web業界で活躍していく場合に必要なスキルは、早めに身につけておくと良いでしょう。
また、Web媒体ではドメイン設定を行う必要があることを留意しましょう。
PDF媒体
PDFポートフォリオの場合には、紙媒体に用いた画像をPDF化しておくと良いでしょう。注意するポイントとして、データを圧縮する必要があります。データが大きすぎると閲覧時に時間を要してしまったり、PDFが開けないリスクが生じてたりしてしまいます。
データをまとめるスキルも評価される場合があるため、要点を押さえたPDF作りを意識しましょう。
ポートフォリオの構成
表紙、プロフィール、目次、得意分野、将来像といった構成のポートフォリオを目指しましょう。順序良く仕上がったポートフォリオは、面接官の印象が良くなり評価も上がります。
ここでは、ポートフォリオの構成について解説していきます。
表紙と背表紙
また表紙、背表紙ともに、見る対象を選ばないシンプルなデザインに仕上げることで、多種多様な面接官に対応できるでしょう。
自分のプロフィール
また、自分の写真を掲載する場合には、ナチュラルな構図と加工を施したものを載せましょう。過剰な加工は、返って印象を悪くする可能性があることから注意が必要です。
[no_toc]
目次
しかし、作品のページごとに番号をふることは避けた方が良いでしょう。ポートフォリオは新卒の面接時だけでなく、転職する際に使われることもあるためブラッシュアップを施します。その際にページ数を変える手間が生じることから、番号はふらない方が賢明です。
自分の得意な制作分野
自己PRに繋がる長所をアピールすることで、企業側にプラスのイメージを与えることができます。特にWeb関連のポートフォリオでは、コーティングなどのスキルを伝えやすいため、実例とともに書き出してみましょう。
志望企業が求めている人材と合致している場合は、それが大きな武器となります。
将来的に目指していきたい方向性
たとえば、Webデザインの企業を志望している場合に、その企業が手掛ける作品をオマージュしたものを載せます。企業側から見れば入社後の活躍がイメージしやすくなり、応募者の積極性を汲み取ってくれる可能性があるでしょう。
また、複数の作品を掲載することで、技量の多さをアピールすることにも繋がります。
ポートフォリオの作品紹介ページで記載したいこと
ここでは、ポートフォリオの作品紹介ページで記載したい内容を細かく解説します。
作品のタイトル
「何の作品か」が相手に伝わるようにするため、文字のサイズやフォント、位置などを工夫します。作品の雰囲気に合った文体とデザインが望ましいですが、過剰に手を加えず、わかりやすさを追求したものが良いでしょう。
また、プラットフォームやジャンルといった補足事項を添えても問題ありません。
プロジェクト概要
なお、情報を簡潔に伝えるために箇条書きや吹き出しなどを用いると、読み手が理解しやすい仕上がりになるでしょう。
作品の画像
載せる画像は何枚でも構わないため、魅力が伝わるような画像を選択しましょう。Webサイトであればいくつかのページを、デザインであれば完成までの工程を載せていくという具合です。その際、画像に関する質問の回答を忘れずに用意しておくと安心です。
また、ネットにアップしているWebサイトや動画を選んだ場合には、URLを併せて記載することも忘れないようにしましょう。
作品の具体的な説明
企業の求人像にフィットした説明を心掛けると良いでしょう。
ポートフォリオを作る際に気をつけたい12個のポイント
たとえば、WebデザイナーであればWebサイト全体のコンセプト設計があるか、適切なコーティングがされているかという点が重視されます。グラフィックデザイナーならば、説得力のあるデザインや、わかりやすいポートフォリオであるかが重要になるでしょう。
ここでは業種を問わず、ポートフォリオを作る際に気をつけたい12個のポイントを紹介します。
[no_toc]
- レイアウトに気を配る
- ユーザー目線で考える
- 作品をジャンルことに分けて紹介する
- Webと紙の両方で作る
- 特に出来の良い作品を強調する
- 作る前に方向性を考える
- 作品を紹介する順番を考える
- プレゼンすることを考えて作る
- 企業ごとに作る
- 作品数は10作品程度にする
- 文章は多くしすぎない
- 常に情報は更新していく
1:レイアウトに気を配る
レイアウトで注意する点としては、余白の大きさを上下左右同じにすることに加え、文字ズレがなく線が繋がっていることです。また、サイトマップの大きさが適切であることや、サイトの全体画像が際立っている、文字を詰め込み過ぎないことが挙げられるでしょう。
作成に入る前にガイドを引くことで、整然なレイアウトに仕上がります。
2:ユーザー目線で考える
自分のスキルや知識をアピールするために情報を詰め込み過ぎると、大変読みにくいものになります。企業側は、応募者のスキルのほかに情報をまとめる能力も見ているため、ユーザー目線で考えられたポートフォリオを高く評価する傾向にあります。
第三者目線というのは自分ではわかりにくいため、制作過程で知人に意見を求めると良いでしょう。
3:作品をジャンルごとに分けて紹介する
ジャンル分けの例として、「イラストレーション」や「エディトリアルデザイン」のように大きく分けたり、「Webサイト」や「バナー」といった細分化したジャンル分けも効果的でしょう。
ジャンル分けは何気ない配慮ですが、見やすさを意識したポートフォリオには欠かせない要素と言えます。
4:Webと紙の両方で作る
同じ業種でも企業によって求められるポートフォリオの形式が異なるため、どちらにも対応できるように準備することが大切です。ある企業では電子メールで送付するケースがあり、また別の企業では面接時にポートフォリオを持参するケースがあります。
就活の幅の拡大にも繋がることから、ポートフォリオは2つの媒体で作成しましょう。
5:特に出来の良い作品を強調する
ポートフォリオは自分の作品をアピールするものですが、ただ羅列しただけでは自分の強みを伝えきれません。出来の良い作品を強調することで、企業側に効率よくアピールでき、良い印象を残すことができます。
また、優れた作品をポートフォリオの前半に配置すると、より効果的に主張できるでしょう。
6:作る前に方向性を考える
ポートフォリオのコンセプトを明確にすることで、一貫性を持った冊子に仕上がり、ブレがなくなります。ページごとに全く異なるデザインやレイアウトの場合、読み手は混乱しやすく、伝えたい作品の印象が薄くなりやすいです。
ポートフォリオ全体の色合いやデザインを統一することで、まとまりのあるポートフォリオが完成するでしょう。
7:作品を紹介する順番を考える
また、企業によって作品を紹介する順番を入れ替える必要はなく、どの企業にも対応できる構成が望ましいでしょう。
8:プレゼンすることを考えて作る
企業が求めている人材は、クライアントの要望を論理的に解決する能力です。さまざまな課題に対して、抽象的ではなく、具体性を持った解決方法が求められるでしょう。
ポートフォリオには、作品が完成する過程で生じた問題と解決方法に加え、その思考プロセスを書き加えると良いでしょう。
9:企業ごとに作る
たとえば、プロダクションであればスキルの幅をアピールし、広告代理店であればアイデアの多さをアピールすることに重点を置くという具合です。企業によってアピールする能力が変わることから、志望企業に合わせた構成を意識しましょう。
10:作品数は10作品程度にする
[no_toc]
面接官は、多くの応募者のポートフォリオを見ているため、1つの作品に時間を費やすことをしません。そのため、作品数が多すぎると正当な評価をもらいにくくなり、逆に少なすぎても情報不足によってアピールが伝わらないでしょう。
一般的には1ページに1~2作品ほど掲載することが良いとされています。
11:文章を多くしすぎない
ダラダラとした文章は読み手に負担を与えるため、要点を簡潔に伝えます。企業は、情報を迅速に正しく伝える能力を求めていることから、小説のような文体はNGとなっています。
文字数に関しては、アピールしたい作品については200文字以上、そのほかの作品では200文字以下が理想です。
12:常に情報は更新していく
特にWeb媒体で制作している場合、Webサイトの情報が最新に保たれていなければ、情報管理能力が甘いと捉われてしまうでしょう。また、紙媒体でも紙質やまとめるファイルの種類などのブラッシュアップが大切です。
ポートフォリオを更新し続けることで、入社後でも活用できる心強い転職ツールとなります。
デジタルでポートフォリオを作る際におすすめのツール
用意されているツールはさまざまあり、目的や用途に合わせて使い分けると良いでしょう。特にビジュアルが求められる業界では、ポートフォリオの見た目も重要になるため、デザインに強いツールを選ぶと作りやすいです。
ここでは、ポートフォリオを作る際におすすめのツールをご紹介します。
Wix
特に、ポートフォリオに写真やイラストの作品を掲載する場合に向いています。デザイナーやクリエイターからの支持が多くあり、高いクオリティのポートフォリオに仕上がるでしょう。
無料でホームページを作成でき、電話によるサポートも充実していることから、初心者にも優しい仕様になっています。
PORTFOLIOBOX
クリエイター全般に適した機能を持っており、カメラマンやアーティスト、イラストレーターなどに対応するポートフォリオを作ることができます。3つの有料プランがあり、それぞれ不随するサービスは異なります。
世界で100万人以上の利用実績を誇ることから、初心者や熟練者問わず、納得のいくポートフォリオに仕上がるでしょう。
salon.io
煩雑なコーティングの知識や難しい操作が必要なく、動画・音声・地図・Webフォントの埋め込みが可能です。無料プランと3つの有料プランが用意されており、プロ御用達の機能やサポートが整っています。
操作の自由度が高いことから、ある程度のポートフォリオの知識が求められるツールと言えるでしょう。
新卒生らしい魅力が詰まったポートフォリオを作ろう
自分の作品を存分にアピールつつ、決められた情報を簡潔に伝えることが求められるため、上手く作成できない場合もあるでしょう。しかし、第一線で活躍している方もポートフォリオ作りを経て今に至ります。
自分の魅力をふんだんに詰め込んで、面接官の心に響くポートフォリオを目指しましょう。