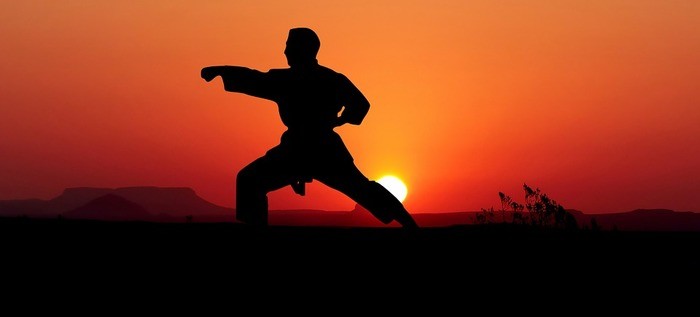[allpage_toc]
「そもそも『押忍』ってどういう意味なの?」
このように、『押忍』という言葉を一度は耳にしたことがあるものの、意味まで理解している方は少ないのではないでしょうか。
普段何気なく耳にしている言葉ひとつひとつには、実は意味があるのです。
本記事では、日常的によく耳にする「押忍」という言葉の語源や由来に加え、「押忍」の持つ意味をさまざまな視点から解説しています。
この記事を読むことで、普段何気なく耳にしている言葉の語源や意味を知ることができるだけでなく、身の回りの言葉の由来にも興味を持つことができるでしょう。
「押忍」という言葉の意味や由来を知りたい方、日常的に使用している言葉の語源に興味がある方は、是非この記事をチェックしてみてください。
「押忍」の語源と由来
実は、「押忍」の語源や由来には諸説があり、主に4つの説があるといわれています。
それでは、「押忍」の語源や由来について詳しくみていきましょう。
海軍の挨拶が短縮された説
「おはようございます」が「おはよーっす」になり、さらに短くなり「おわーす」、そして「おす」のように変化したようです。
さらに下記でも詳しく説明しますが、簡略化した「おす」に武道の精神である、「自我を抑えて我慢する」という意味の、「押して忍ぶ」を漢字として当てはめたことから、漢字で「押忍」と書くようになったといわれています。
拓殖大学発祥説
中高年のためのキックボクシングイベントである「NICE MIDDLE」を主宰している大森敏範は、自身の著書『押忍とは何か?』で相撲の心得が「押忍」の由来になったと記しています。
現在の拓殖大学では、体育会を中心に学生間でのあいさつとして「押忍」が親しまれているようです。
佐賀の藩校発祥説
佐賀の藩校では、山本常朝の有名な著書『葉隠』の中で書かれている武士の精神を模範とし、武士たちに厳しく教育を行っていました。
厳しい教育の中、武士たちがお互いを励まし合う意味で「押忍」と声を掛け合ったといわれています。
京都の武道学校発祥説
かつて京都府左京区にあった武道専門学校で「押忍」が使われていたようです。
今では先輩から後輩にするあいさつとして使われることが多い「押忍」ですが、当時の学生たちは後輩から先輩にあいさつを返す時に「おっす」と言っていました。
のちに前述にもある、「自我を抑え我慢する」という意味の「押」「忍」を当てはめたとされています。
「押忍」の意味とは?
上記で述べた語源や由来からも、「押忍」があいさつを意味していることが分かりますね。
また、「押忍」は「押」と「忍」の漢字二文字で構成されています。
「押」には相手に対して働きかける、方針を変えずに貫く、やり方などを変えずに進める、という意味があり、「忍」には気持ちを抑える、痛切な感情を表わさないようにする、という意味があります。
この二文字から、「押忍」という漢字には「相手に対する気持ちをおさえて我慢する」という意味が込められていることが分かります。
「押忍」が使われる場面
[no_toc]
そのほかにも、後輩から先輩にあいさつを返す時にも「押忍」が使われています。特に体育会系の学校や部活動でよく聞くあいさつですね。
このように、「押忍」はさまざまな場面で使用されていることがわかります。
武道で使う「押忍」の意味
具体例をひとつ挙げましょう。
仕事やプライベートで、辛いことや悲しいことがあったとします。そんな時、あなたはどのように状況を乗り越えますか。自分の不運を呪う人もいれば、現実から目を背けて逃げてしまう人もいるのではないでしょうか。
そんなとき逃げだすことなく、かといって単に我慢するのでもなく、前向きで謙虚な気持ちを持って耐えることこそが「押忍」なのです。
空手道における押忍が持つ意味
積極忍耐
反対に、他人任せで状況を自分でコントロールすることができない忍耐は消極忍耐です。
「自我を抑え我慢する」という考えは武道の精神にもつながっています。「押」と「忍」の2つの漢字が当てはめられたということは、ただ耐えるだけの「忍」だけでなく、積極的に「押」ことも大切だということです。
単に何もしないで好機を待つのではなく、希望を持ち積極的に待って堪え忍ぶことは空手だけでなく、さまざまな物事において重要な考え方ではないでしょうか。
自己鍛錬
いざというときに、自分自身や大切な人を守れるように戦える強靱な肉体を日々の鍛錬でつくり上げているということなのでしょう。
そもそも、精神が強くないと強靱な肉体をつくることはできません。生半可な気持ちでは、全てが中途半端になり極限状態で戦うことはできないでしょう。
仕事でもプライベートでも諦めることは簡単ですが、困難を乗り越えないと目標は達成できないですよね。
自己鍛錬は空手でよく耳にする言葉ですが、実生活に置き換えて考えてみるのも良いかもしれません。
日常への尊敬の念
日常で使わないからこそ、非日常で自分を高めることのできるスピリチュアルな側面を持ちます。
そんな押忍の精神性に触れることによって、日常や現実への尊敬の念を忘れないためにあるともいわれているのです。
「押忍」を使ってみよう!
「押忍」にはさまざまな意味があり、ただ単にあいさつとして用いられるだけでなく、武道では精神世界と深いつながりを持つ意味の言葉として使用されています。
このように、「押忍」だけでなく、日頃よく耳にしている言葉のひとつひとつにはそれぞれ独自の意味やルーツがあります。
言葉本来の意味を理解した上で、あなたも「押忍」を日常生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。