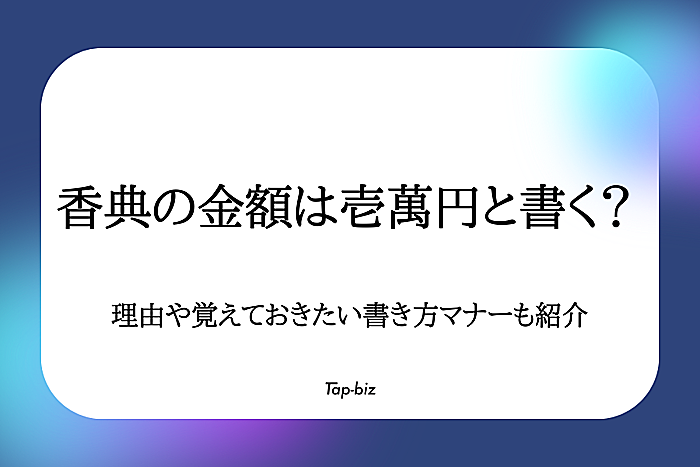[allpage_toc]
「香典を用意するときのマナーってあるの?」
「香典ってどうやって渡せばいいの?」
このように訃報は予測できないため、いざ香典を用意する段階になってわからないことが多く困ってしまったことはありませんか?
この記事では、香典を準備するところから渡すまでの基本的なマナーを紹介していきます。香典袋の書き方やお金の入れ方、香典の渡し方などの一般的なマナーを知ることができるでしょう。
香典には様々な注意点があるため、間違いがないか、相手に失礼がないかなどの不安を感じる方も多いと思います。記事の中では香典に関連する覚えておきたいマナーも解説します。
マナーを知らないと自分が恥をかくだけでなく、相手に不快感を与えてしまいます。記事を読んで香典のマナーをチェックしてみてください。
香典で目にする「一万円」の書き方の種類
香典袋には香典の金額を記入する必要がありますが、金額の書き方にも種類があります。
香典に入れた金額を中袋に漢字で縦書きしますが、一万円であれば「壱萬円」、「壱万円」、「壱萬圓」などと書くのが一般的です。
丁寧な印象がある「壱萬円」
縦書きで漢数字を使う点がポイントです。この書き方は「大字」と呼ばれる難しい漢数字を用いています。
丁寧な印象になりますし、一般的な書き方といえるでしょう。
シンプルで見やすい「壱万円」
「萬」という漢字に馴染みが薄いため、「万」と記入する場合も増えてきました。
シンプルで見やすくわかりやすい書き方になります。
統一感がある「壱萬圓」
漢数字も「円」も大字を使っており、より丁寧になります。
香典で壱萬円や壱萬圓を使ったほうがいい理由
複雑な大字を使うことで、金額の改ざんができないようにするためです。
例えば漢数字の「一」であれば、縦線や横線を足すだけで簡単に「三」や「十」などに書き換えることができてしまいます。
このような事態を避けるためにも、正しい書き方を覚えておきましょう。
香典袋の中袋の書き方
中袋はお金を入れるための封筒で、金額と名前、住所を記入します。
外袋は薄墨を使って書きますが、中袋は香典を受け取った人がわかりやすいようにペンを使って記入するのが一般的です。
ここでは中袋の金額の書き方について詳しく紹介していきます。
金額を書く場所
数字の書き直しなどのトラブルを防ぐために、「一」や「二」などの常用の漢数字ではなく、「壱」や「弐」などの大字を使って書くのが基本的なマナーです。
また、金額の前には「¥」と同じ意味合いで「金」、金額の後ろには「圓」もしくは「円」と書きます。
お通夜や葬儀は受付があり、遺族に直接香典を渡せないことが多くあります。また自宅での葬儀の場合は仏前に備えることが多く、大金が入っている香典袋がそのまま置かれることもあります。
自分がいくら包んだのか改ざんのできない旧字体で書くことで、不要なトラブルを避けることができます。
なお、記入欄が印刷されているタイプの香典袋の場合は、金額を横書きすることもあります。その場合は漢数字ではなく算用数字を使って記入します。
「也」の有無
[no_toc]
「也」があることで礼儀正しくはなりますが、必ず必要というわけではありません。
もともとは金額の書き換えがないように、高額な香典につけることが習慣としてありましたが、現在では特に重んじられていません。
香典袋の名前の書き方
個人で香典を包む場合は、水引の下の真中に名前を書きましょう。遺族が香典返しをする際わかりやすいように、フルネームで書くのがマナーです。
また、代理で香典を渡す場合は、香典費用を負担した人の名前を記入し、その左横に「代」と記載します。
会社で香典を包む際には、会社名とあわせて代表者名を書くのが一般的です。部署など4人以上で用意する場合は「〇〇部一同」などと書くのが良いでしょう。
団体や連名などで用意した場合には、遺族がお礼状などの手配をしやすいように、中袋に代表者の名前や連絡先を必ず書くようにしましょう。
香典袋の住所の書き方
金額は大字で記入しますが、住所は普通の漢数字で書きます。
中袋がない場合には、香典袋の裏側に、水引より下の左側に住所を記入しましょう。
また、横書きの記入欄がある場合には、住所の数字は漢数字ではなく算用数字を使っても構いません。
覚えておきたい香典の書き方マナー
遺族への気遣いや故人を弔う気持ちを大切にするだけでなく、基本的なマナーを守って香典を準備することが必要です。
ここでは覚えておきたい香典のマナーについて紹介します。
表書きは宗教や宗派によって変わる
例えば仏教であれば「御霊前」や「御仏前」と書くのが一般的ですが、神式であれば「御神前」や「御玉串料」などと書きます。
仏教やキリスト教、神式など、葬家がどの宗教を信仰しているのか確認してから準備するようにしましょう。
また、どうしても相手の宗派がわからない場合は「御霊前」と書くのが一般的です。ただし、浄土真宗やキリスト教のプロテスタントでは使用することができないため、注意しましょう。
基本的には薄墨を使う
慶事では普通の濃い墨で書きますが、弔事では「悲しみの涙で墨が薄くなってしまった」という意味や、「急な訃報に、墨を濃くする時間を惜しんで駆け付けた」などという意味から、薄墨で書かれるようになりました。
このような理由から、訃報を聞いて駆け付けるお通夜や葬儀の香典に限り薄墨を使用し、初めから予定が決まっている法要では薄墨は使いません。
また薄墨を使う場合でも、住所や香典金額については読みづらくなりがちな薄墨ではなく、書きなれた万年筆やボールペンなどを使うとよいでしょう。
香典袋は宗教や金額にあったものを使う
宗教や宗派によって「御霊前」や「御玉串料」などと表書きを使い分ける必要があることは前述してありますが、香典袋の絵柄も宗教によって違いがあります。
香典袋には多くの種類があり、一般的な無地の包みのほかに、十字架や蓮などの絵柄がついたものもあります。
無地の包みであれば、どのような宗派であっても利用できるため、故人の宗派がわからない場合は無地の包みを選んでおくのが無難でしょう。蓮であれば仏教、十字架であればキリスト教、などと宗派独特の包みもあるため、選び方には注意しましょう。
また香典袋の水引の形は、二度と繰り返さないようにという意味から、解けない結び方を選びましょう。解けない結び方には「あわじ結び」や「結び切り」があります。
包む金額が5千円くらいまでは水引がプリントされたタイプを使用し、実際に水引が結ばれているタイプは1万円以上を包むときに使います。
香典の渡し方
まず香典を持参する場合は、紫色や茶色などの袱紗に包みます。香典袋を素手で持ち歩くことや、華やかな色合いの袱紗に包むのは避けましょう。
お通夜や葬儀の場合は受付で渡す場合が多くありますが、その際香典を素手で触らずに袱紗ごと持ち、香典のみ手渡します。その際、「この度はご愁傷さまです」などとお悔やみの言葉を一言添えるとよいでしょう。
[no_toc]
香典袋にお金を入れる際に注意したいこと
小さな心遣いかもしれませんが、遺族や故人に対して失礼にならないように、香典のマナーを知っておきましょう。
新札を包まないようにする
慶事のお祝いの際には、折れ曲がっていない新札を包むのがマナーですが、弔事の場合は新札を入れると遺族に対して失礼に当たります。これは、故人の死を事前に予期していたと感じさせるためです。
もし手元に新札しかない場合には、一度折り目をつけてから香典袋に包むようにしましょう。
また、新札を包むのが失礼に当たるからといって、落書きやあまりにもボロボロなお札を使うのも避けましょう。汚すぎるお札も遺族にいい印象は与えないため、注意しましょう。
お札の向きや枚数に気をつける
香典袋の中袋を表側にしたときに、お札の肖像画がない裏側が前になるように入れましょう。このときお札の裏側の肖像画は下向きとなります。反対向きに入れてしまうとお祝いの意味になってしまうため、注意して包みましょう。
包む際には、すべてのお札の向きがバラバラにならないようにしっかり揃えましょう。
また、お札の枚数は偶数ではなく奇数になるように包むのがマナーです。偶数は割り切れるため「縁が切れる」といわれるためです。例えば2万円を包む場合には、1万円札1枚と5千円札2枚の合計3枚にするなどの配慮をしましょう。
縁起の悪い枚数も避けた方がよいでしょう。奇数でも、「死」を連想させる4や、「苦」を連想させる9は避けて遺族に失礼のないようにしましょう。
香典で壱萬円と書く理由やマナーを押さえておこう
香典とは故人への供養の気持ちと、遺族への助け合いの意味を持つ、昔からの大切な慣習です。そのため、故人と遺族に対して失礼がないよう、最低限のマナーを守ることが大切です。
予測できない不幸ごとだからこそ、いざというときに慌てず落ち着いてお悔やみの気持ちを伝えられるように、香典に関するマナーを理解しておきましょう。