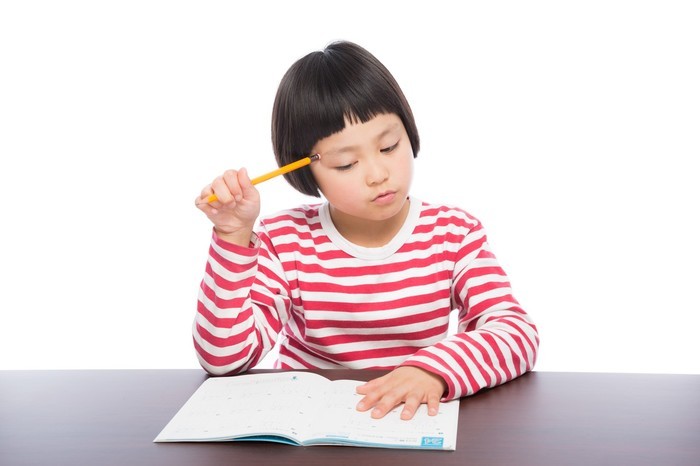[allpage_toc]
論じるとはどういうことか?
論じるときの書き出し方は?
テーマが明確な場合!
テーマがはっきりとしています。そこで、この場合は「結論から書き出す」ようにします。回答例をお示ししましょう。
1.私はビートルズが世代を超えて人気があるのは、メロディーラインやリズムが、いつの時代の人にも心地よい感覚を与えるからだと考える。
2.ビートルズが世代を超えて人気があるのは、メロディーラインやリズムが、いつの時代の人にも心地よい感覚を与えるからだと考える。
ここでのポイントは、結論から論じるスタイルは同じですが、文頭に使う言葉として、「私は」または問題の中の言葉(例題の場合はビートルズ)を持ってくるということです。
テーマが漠然としている場合!
テーマが漠然としています。こんな場合の書き出しは「自分が想定した問題提起」です。回答例をお示ししましょう。
1.なぜビートルズは、世代を超えて人気があるのだろうか。
2.なぜビートルズの曲のメロディーやリズムは、現在も色あせることがないのであろうか。
このように、ビートルズに関して、自分自身が持つ問題意識や疑問を冒頭に持ってきます。よく、「私は、ビートルズが世代を超えて人気がある理由をこれから書いてみる」という表現をする人がいます。間違いとは言えませんが、幼稚な印象を与えてしまします。原則的には「~だろうか」、「であろうか」と表現します。
論じるときの語尾は?
調子を合わせる!
あいまい表現はしない!
この場合は、「~である」、「~ということだ」というように断定的に言い切るようにしましょう。全くの事実誤認の場合はNGですが、思い切って断定しても問題がない場合は自信を持って断定して「論じる」ようにしましょう。
肯定文で書く!
肯定文=断定的ですから、情報量としても多く論旨も明確になります。もちろん、否定的な言い回しをしなければならない場合もありますが、「原則は肯定」と覚えておきましょう。
[no_toc]
能動態で!
しかし、「論じる」相手はレポートや課題などであり、「採点」の対象になる文章です。より自然で読みやすい能動態表現で論じるようにしましょう。
「論じる」ときの語尾以外の注意点は?
読みやすさ!
そのためには、常に相手の立場にたって、どのような表現をすれば誤解されずに真意が伝わるのか、どのような言い回しが相手にとって読みやすいのかなど、常に相手目線で文章を書くことが基本です。
文は簡潔に!
1つのセンテンスは、長くても2行程度としましょう。長くなりそうであれば、一旦区切って、複数のセンテンスになるようにしましょう。
修飾語の使い方!
「星のようにきらめく夜景を見ている君を見た」。この文では、「星のようにきらめく夜景」を見ている「君」を見たという解釈(星のようにきらめくのは夜景)と、「星のようにきらめく「夜景を見ている君」を見た」(星のようにきらめくのは「夜景を見ている君」)という二つの解釈ができてしまいます。
どうでしょうか。ここまで気配りをして修飾語を使っているでしょうか。例えば、前者の意味で使いたい場合は、「星のようにきらめく夜景を、見ている君を見た」となります。また、後者ならば、「星のようにきらめく、夜景を見ている君を見た」というように、表現になります。句読点を効果的に使うと意味が明確になります。
誤字・脱字・読みづらい字はNG!
また、理解の範囲を超えているであろう横文字を、しかも複数使用するのもNGです。読み手も理解できない場合がありますし、内容よりも言葉でごまかそうとしているのでは、との疑念を抱かせてしまう恐れもあります。
論じるときの考えの書き方は?
疑問の連鎖で考えを深掘りする!
・自分がそのような考え方をしたのはどういう時か。
・日常生活の中で、自分が嘘をついて公開するのはどんなケースか。
・周りに問題のような人はいるだろうか。
・その人たちはなぜそのように考え、行動するのだろうか。
というように具体的な疑問を想定し、Q&A方式でメモを取ります。
ポイントは、疑問→答え→それに対する疑問→答えというように、「なぜの連鎖」をしてどんどん深掘りしていくことです。深掘りすればするほど、より客観的な事実(真実)に近づきます。
6つの視点を持つ!
[no_toc]
1.事実を知る:その問題・テーマをめぐる事実を把握する。
2.背景から考える:その問題はどんな背景から生まれたのか、時間をさかのぼってリサーチする。
3.別の立場で考える:賛成・反対など立場の違う人の多様な意見を聞く。
4.規模を広げて考える:日本に関する問題の場合は世界との、地方に関する問題の場合は全国との比較をするというように、規模を広げて考える。
5.プロの見方を参照する:専門家の視点を借りて、本質や外せないポイントを押さえる。
6.常識を疑う:思い込みを覆して新しい発想を生み出すようにする。
これら6つの視点から疑問を持つことで、客観的な事実を把握することができ、より説得力のある文章を書くことができるようになります。
論じるときのコツは?
PREP法の活用を!
(1)結論をまず述べる:一般的に、人は一番最初の文章の読み始めや、話し出しの30秒程度が特に集中力が高いと言われています。「論じる」場合は結論を最初に述べましょう。
(2)相手の疑問を先回りする:結論から先に述べられると、「なぜ」と突っ込むのが人間の心理です。そこで、結論の次にその理由を持ってきます。その際に重要なのは、できるだけ具体的かつ客観的な根拠を持って説明するということです。根拠のない理由では説得力はありません。
(3)抽象と具体の往来:PREP法では、抽象的な結論から始まって具体的な理由を述べ、最後に抽象的な結論に返ってくることで、文章に安定感を持たせ、読み手にも安心感を与えます。
PREP法を活用して「論じる」コツを習得しましょう。
テストの事例!
1.賛否両論ある:一般的に見解が大きく偏る問題提起は避けるべきです。普通の見方と異なる見解が出しづらく、当たり前の意見となって評価が得にくいからです。
2.身の丈に合っている:時間内に「論じる」必要があるので、調べないと分からないことは書かないのが鉄則です。
3.社会にとって大事なこと:個人的な趣向ではなく、社会全体にとってプラスかマイナスかという視点で問題提起するようにしましょう。
論じるときの書き方の例は?
レポートの書き方は?
次に本論ではその理由を述べます。説得力を持たせるために資料や文献を引用します。根拠を述べた後は必ず自分の見解を書きます。その際に異なる意見に対する自分の見解を、論理的かつ合理的に述べるようにしましょう。
最後に結論です。最初の繰り返しになりますが、レポートを通して自分が伝えたいことや今後の展望と課題、レポート作成を通じて感じたことなどを書けば文章が引き締まります。
課題の書き方は?
この関係を押さえておかないと筋の通らない文章になります。ポイントは、・そもそも何が問題なのか、・その問題を解決するためには何を目標にすべきなのか、・課題を解決するために、いつまでにどのようなことをしなければならないのかという点を明確にしましょう。