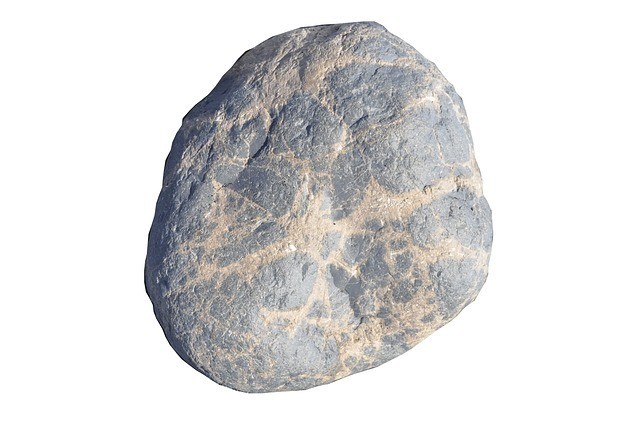[allpage_toc]
「石を投げなさい」の意味と使われ方とは?
これは、イエス・キリストがパリサイ人や宗教指導者に対していった言葉とされています。姦淫の罪を犯したとされる女性を前にして、イエスが「あなた方の中で罪のない人が、彼女に対して最初に石を投げなさい」と言った記述から来ています。
それで一般的には、誰でも神のみ前では罪人で自分も失敗をするのだから、他の人の罪を許しなさいという意味だと理解されています。私達も神から罪を許していただくことを望んでいるでしょう。
「石を投げなさい」の由来・元ネタは?
ですから、正確には「石を投げなさい」とイエスが言った言葉とは言い切れませんが、そのことを踏まえた上で、この言葉の意味を説明いたします。
イエスの生きた時代である1世紀当時、パリサイ人や宗教指導者たちは、イエスの言葉尻をとらえてイエスを陥れようとしていました。
そこで彼らは、姦淫の罪を犯した女性を連れてきて、「モーセは律法の中で、このような女を石打ちにすることを私たちに規定しました。あなたはいったい何と言われますか」とイエスに挑戦的に問いかけました。そこでイエスが、「罪のない人が石を投げなさい」と言ったという話が由来となっています。
「石を投げなさい」に関する誤解
この姦淫をしたとされる女性の名前は聖書には出てきません。しかし、この女性がマリア・マグダレネ、もしくはマグダラのマリアという名前の女性だと主張する宗派があります。イエスを描いた映画の中に、この話が付け加えられているものもあります。
このマリア・マグダレネとは、イエスの死の際と復活の際に居合わせた女性のうちの一人です。それ以前、彼女は七つの悪霊をイエスに追い出してもらいました。その後、熱心な信者になりました。
しかし、このマリアは姦淫を行っていたという記述はありません。ですから、この「石を投げなさい」の逸話に登場する女性とは関係ありませんので、混同しないようにしましょう。
「石を投げなさい」とイエスが言った言葉の意味は?
その律法の中で、重大な犯罪とされているものの中に姦淫がありました。聖書の中では、姦淫とは既婚者が自分の偶者以外の異性と性関係を持つことを指します。この罪を犯した人は、裁判にかけられ死刑が決定したなら、石打ちによって処刑されました。この処刑が適用されたのは、重大な罪を故意に犯した場合のみでした。
イエスの言った「石を投げなさい」というのは、処刑しなさいという意味です。しかし、「罪のない人が」と条件を出したので、ここで言う罪とは何かを理解する必要があります。
罪とはどういう意味か?
では、イエスが「罪のない人は石を投げなさい」と言った時の罪とは、どのような意味でしょうか。聖書の中では、罪には、上記で説明した姦淫などの重大な罪という意味だけでなく、「不完全」という意味もあります。人はだれでも生まれながらに罪人、つまり不完全で間違いや失敗をします。
ですから「罪のない人」とは、失敗も間違いも犯さない完璧な人ということです。しかし、そのような人は地球上に存在しません。つまり、「罪のない人」はいないということです。
「石を投げなさい」の聖書のあらすじ
イエスは、ある時オリーブ山で民衆を教えていました。そこへパリサイ人が、姦淫の場で捕らえた女性を連れて来ました。彼女を真ん中に立たせてから、イエスに「モーセは律法の中で、このような女を石打ちにすることを私たちに規定しました。あなたはいったい何と言われますか」とイエスに問いかけました。
しばらくして、イエスは「あなた方の中で罪のない人が、彼女に対して最初に石を投げなさい」と言いました。すると、パリサイ人や他の人達は皆去って行きました。
一人だけ残った女性に対して、イエスが「彼らはどこにいるのですか。誰もあなたを罪に定めなかったのですか」と問うと、「誰も」と女性は答えました。イエスは「私もあなたを罪に定めません。行きなさい。今からは、もう罪を習わしにしてはいけません」と言いました。
前後の出来事
この当時、パリサイ人や宗教指導者達のイエスに対する敵意が高まっていました。彼らはイエスを捕らえようとしていましたが、イエスは大胆に伝道し、多くの民衆を引きつけました。
イエスは各地を回り、パリサイ人や宗教指導者とは全く違う方法で民衆を教えてました。イエスの教えは論理的であり、民衆の心を癒す心地良いものだったので、従う弟子はどんどん増えて行きました。
また、イエスは、奇跡を行って病気の人を癒したり、死人を復活させたりしました。多くの人がイエスを支持するのを見て、パリサイ人たちはいらだっていました。それで、イエスを石打ちにしようとたくらんでいました。
ところで、パリサイ人とは一体どのような人達だったのでしょうか。なぜ、そこまでイエスを憎んでいたのでしょうか。
パリサイ人とは?
なぜ、彼らはイエスを捕らえようとしていたのでしょうか。それは、イエスの教えが素晴らしく、多くの人が追随者になっていたからです。また、自分たちの悪事が暴露され、地位や名声を失うことを恐れていたことも理由です。
例えば、あるときパリサイ人達がイエスを捕らえるために下役達を遣わしました。しかし、下役達はイエスを捕らえずに戻ってきました。「なぜ彼を連れてこなかったのか」と聞くと、「あのように話した方はいまだかつてありません」と下役達は答えました。イエスの教え方に感動し捕まえることができませんでした。
[no_toc]
「石を投げなさい」から学ぶ教訓とは?
人はみな罪人です。つまり、完全ではないので間違いや過ちを犯します。ですから、イエスの「石を投げなさい」の逸話には、自分も間違いを犯すので、他の人の過ちを許すようにという教訓が含まれています。
パリサイ人も、厳格に自分たちの伝統を守るように民に強要していましたが、姦淫をした女性が重大な罪を悔い改める意思があるのなら許し、清い生活を送るチャンスを与えるべきでした。
私達が過ちを犯したときには、神にも他の人にも許してもらうことを期待します。そうであれば、他の人の過ちに対しても寛容な態度、つまり許すという態度を示すように努力すべきです。相手が過ちを深く悔いているならなおさらのことです。
怒りを宿すのではなく、人を許すことは、相手と自分の精神衛生上非常に大切なことです。
「石を投げなさい」の教訓をビジネスに生かす
自分の売り上げや儲け・利益だけを考えた強引なやり方は、結果として顧客を失うことになります。人間味のある対応をすれば、お互いに気持ち良く商談を進めることができるでしょう。利己的なパリサイ人のような態度は避けましょう。
また、同僚の仕事のミスを許すことも必要です。誰でも失敗はあります。完璧な人は存在しないからです。自分も仕事上のミスをしたことは多々あるのではないでしょうか。特に新人の頃、先輩や上司や顧客に迷惑をかけてしまったこともあるでしょう。そのような時、それを見逃してくれたり、かばってくれた人がいたのではないでしょうか。
「石を投げなさい」の逸話を思い出し、情状酌量の精神を示していきましょう。
「石を投げなさい」に関するジョークは?
一つは、「罪のない人が石を投げなさい」と言った後、罪のない人イエスだけが石を投げていたというジョークです。
もう一つは、各国の国民性に関するジョークです。「たとえ心の中ででも姦淫を犯さなかった者だけが石を投げなさい」と言ったイエスに対し、アメリカ人は心の中というプライバシーを侵害されたとして、イエスを訴えました。
ドイツ人はしばらく考えて、規則だからと石を投げました。フランス人は、心の中の姦淫という甘い罪を責めたとしてイエスに石を投げました。日本人は、みんなが投げているからと石を投げました。イタリア人は、さっそうと現れて女性を救ったとイエスに感心したが、罪が何かは分かっていなかったということです。
注意点
海外では宗教に関する考え方が日本人とは違う場合が多いことを覚えておきましょう。日本では仏教・神道の国ですが、実際には無宗教の人も多いでしょう。普段の生活に宗教が大きく関わっているわけではありません。
しかし海外では、信仰を非常に重視する文化もあります。日常の会話でも神・イエス・聖書といった言葉を頻繁に使います。そのような人と接する時は、敬意を示すべきです。コミュニケーションを円滑にするには、相手の宗教信条に対する敬意も必要です。
世界には多くの宗教が存在します。国際的な教養ある人として、グローバルなビジネスを展開したければ、宗教に関する理解も不可欠と言えるでしょう。
他の聖書由来の日本のことわざって?
ところで皆さんは、聖書をお読みになったことがあるでしょうか。なんだか難しそうというイメージを持たれている方も多いでしょう。
しかし、実は聖書の中には、他にも日常生活や人間関係、そしてビジネスにまで活かすことのできる大切な教訓がたくさん含まれています。自分がどんな宗教観を持っているかに関わらず、聖書に関する教養を身につけておくことは、心を豊かにするのに役立つでしょう。
聖書の中には、日本人も知らず知らずのうちによく使っている言葉もあります。聖書から取られた言葉だと知って驚かれる方も多いでしょう。「石を投げなさい」だけでなく、他の記述も少し見てみましょう。
ここでは、日本人になじみのある「豚に真珠」と「目からウロコ」について紹介します。
豚に真珠
この言葉の由来は、マタイによる福音書7章6節に書かれてある「神聖なものを犬に与えてはなりません。あなた方の真珠を豚の前に投げてもなりません。彼らがそれを足で踏みつけ、向き直ってあなた方をかき裂くことのないためです」という記述です。
これは、山上の垂訓という有名な場面でイエスが語った教えの一つです。イエスの人類に希望をもたらす素晴らしい教えも、価値を認識しない人にとっては意味のないものであるという現実をイエスは知っていました。
理解できる人に、価値あるものを分かち合うべきという教訓を含んでいます。
目からウロコ
この言葉は、使徒9章18節にある記述に由来しています。キリスト教徒を迫害していたサウロという人物が、旅をしていると天から光があり、復活したイエスの声を聞きます。「なぜあなたは私を迫害をしているのか」と言われ、盲目にさせられます。
そして、アナニヤという人が遣わされ、サウロに手を置くと、サウロの目からうろこのような物が落ち視力を取り戻します。サウロは改宗し、パウロとして熱心に宣教するようになります。
このことから、あることをきっかけとして、理解の目が開けることを意味します。このような経験をすると疑問の答えが分かり、すっきりした気持ちになり、知識が結びついてきます。社会人として学び続けることをやめなければ、「目からウロコ」体験ができ成長できるでしょう。
「石を投げなさい」を正しく理解しグローバルな人間になろう!
他の人に対して厳格すぎる要求をするのは、理不尽であることも学びました。自分も間違いや失敗をする人間であることを認める謙虚さも必要です。
この「石を投げなさい」から学んだ教訓をビジネスに生かすことができれば、人間関係を円滑にするのにも助けになります。
また、聖書や宗教に対する理解を深めておくことも、国際的な視野を入れたビジネスには欠かせないものと言えるでしょう。今回紹介した情報を生かし、グローバルな人間に成長してください。