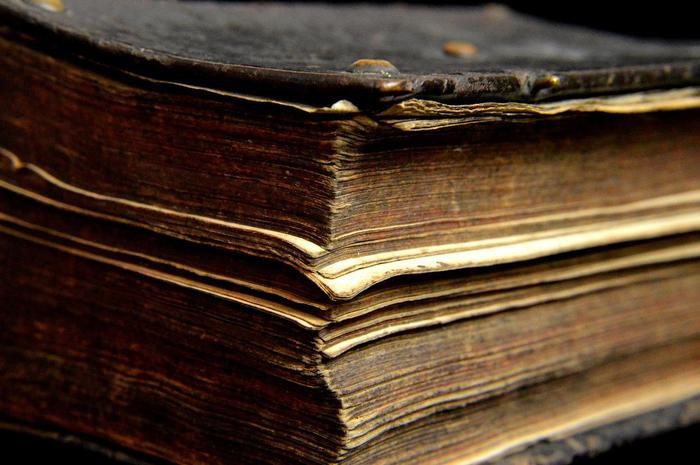[allpage_toc]
「せうはどういったケースで使われていたのだろう」
「古文で見たことあるけど現代でも使われているのか知りたい」
など、古文を学ぶとたくさんの疑問が出てくるのではないでしょうか。
古文を楽しむにはせう・にほひなど歴史的仮名遣いの正しい使い方を知る必要があります。
特に、せうの意味は複数あり勉強しても疑問が解消されない人が多いようです。
また、せうは方言として現代でも使われています。方言のせうは、古文でのせうと意味が違うため混乱してしまうことも多いでしょう。
本記事では、古文で使われているせうとその意味、方言としてのせうと使い方を紹介します。
この記事を読めばせうの正しい意味と方言としてのせうの区別ができるようになるでしょう。
古文を勉強している人はぜひ参考にしてください。
古文などでよく使われている「せう」
しかし、です・ますのように誰に対しても使えるわけではないため注意が必要です。
以下にせうの意味と使い方を紹介します。
意味と使い方
たとえば勉強しましょう、という文は古文では勉強しませう、になります。
また、せうの後にかをつけると相手への問いかけになります。古文を勉強しませうか、は古文を勉強しませんか、になるわけです。
せうは古文における文末表現の1つなのです。
歴史的仮名遣いとしての「せう」
しかし、以前の日本では使われていました。
以下に歴史的仮名遣いの概要と現代仮名遣いの関係を紹介します。
歴史的仮名遣いとは
仮名遣いとは書き言葉独特の仮名の使い方のことを指します。
たとえば、王様という言葉はおうさまと書きます。しかし、発音はおおさまです。また、おーさまと読んでも意味は通じます。
ただし、書き言葉でおおさま・おーさまと書くと間違いになります。仮名遣いとは、おうさまのように書き言葉での仮名の使い方を指すのです。
歴史的仮名遣いは、現代仮名遣いより大きく変化します。たとえば、せうの他にもにほひ・よろづなどが歴史的仮名遣いになります。
歴史的仮名遣いは古文では必須になるため覚えておきましょう。
歴史的仮名遣いから現代仮名遣いへ
歴史的仮名遣いのままだと意味がわかりにくいため現代仮名遣いに直す必要があるのです。
たとえば、にほひはニオイ、よろづはヨロズというように変換します。
また、歴史的仮名遣いは現代と意味が違う事も多いため注意しましょう。にほひは美しいという意味で、よろづは現代で使われるあらゆるものを指すのではなく、たくさんあることを意味します。
歴史的仮名遣いのせうは目上の人に対して使います。せうはいきませう(いきましょう)勉強しませう(勉強しましょう)というように文末表現として使われているのです。
その他「せう」で使われる古語
古文のせうは現代では使われないため、戸惑う人も多いでしょう。
古文で使われるせうは5つに分類されます。古文を読む際は混乱しないように注意しましょう。
以下に、せうの使い方を紹介します。
[no_toc]
「せう」(小)
小さいという意味のせうは他のせうより多く登場する言葉です。
徒然草で、人に先立ちて、せうを捨て大につくがごとしという文が出てきます。
現代文に翻訳すると、相手に先んじて利の少ない方を捨て大きい方につくのと同じという意味になります。
「せう」(抄・鈔)
注釈した書物を指す場合、論語抄・史記抄・三略抄・杜詩(とし)抄・碧巌(へきがん)録抄・貞永(じょうえい)式目抄など原点名に抄が付きます。
「せう」(簫)
簫の歴史は長く中国の宋代には使われていたようです。簫は竹でできており両手で持つ縦吹きの笛のことを指します。
簫の笛(しょうのふえ)とも呼ばれ現代でも使われている管楽器です。
「せう」(少輔)
少輔は律令制で定められた八省の次官の位を示します。少輔は作品によって全く使われない言葉です。
少輔は、せふ・せういう、とも呼びます。1つ上の位は大輔(たいふ)です。
「せう」(兄鷹)
弟鷹(だい)はメスの鷹を指します。
兄鷹という文字の由来は、鷹のオスはメスより小さいためオスの鷹を小(しょう・せう)といい、これに兄を当てた説と、妹(いも)に対する兄(せ)に関係づけて説明する説があり正確にはわかりません。
古文の作品によっては兄鷹と弟鷹を区別しないと理解できない部分が出てくるため混同しないようにしましょう。
長野県の方言としての「せう」
方言のせうは歴史的仮名遣いのせうとは意味・使い方が全く違うため混同しないようにしてください。
以下に、方言としてのせうの意味と使い方を紹介します。
[no_toc]
意味と使い方
方言のせうは言うの他に話す、しゃべるというように解釈されます。方言のせうは歴史的仮名遣いのせうとは違い活用形があるため難しいと感じる人もいるでしょう。
方言のせうはおもに長野県北信州で使われています。
方言としてのせうの基本活用は、せわない・せいます・せう・せうとき・せえば・せえです。
方言の「せう」を使った例文
よく例として使われるのは、せったかせわぬかという文です。
これは、言ったか言わなかったかという文になります。
せうの過去形はせったです。上の例文の場合、せうの過去形せったが使われているため言ったと訳しましょう。
「せう」の正しい意味を知って理解しよう
古文の場合、せうはしょうと直され、意味はです・ますです。目上の人に対して使われます。
また、古文のせうは文末表現以外も、小さい・劣っているといった使われ方をします。古文のせうは他に笛や鷹といった固有のものを指すので注意しましょう。
せうは古文の他に方言として使われます。言う・話す・しゃべるという意味で使われるため古文と完全に別物として考えましょう。
これらをおさえればせうの正しい意味が理解できます。ぜひ参考にしてください。