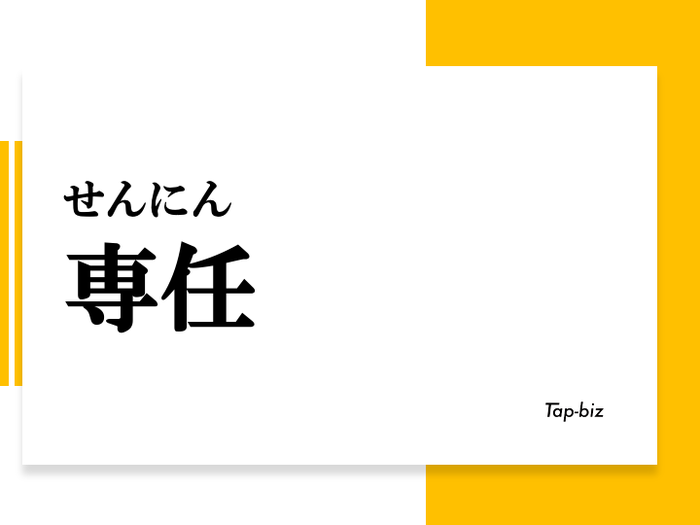[allpage_toc]
「専任と専従ってどう違うの?」
このように、様々な場面で見かけることがある専任という言葉の意味について、疑問や興味を持っている人もいるのではないでしょうか。
本記事では、専任という言葉の意味に関する基礎的な知識とともに、専任の対義語とその意味、さらに似た言葉である専従との違いについて環境による違いを含めて解説しています。
この記事を読むことで、専任がどのような意味合いで用いられている言葉なのか、理解することが可能です。その知識をもとに、専従との違いや専任の対義語について理解し、環境によって正しく使うことができるようになるでしょう。
専任という言葉とその意味について興味がある人は、ぜひこの記事をチェックしてみて下さい。
「専任」の意味とは?
「専」は「もっぱら」や「そのことだけをする」という意味を持つ漢字であり、「任」は「仕事」や「役目につく」という意味を持つ漢字であることから、専門の任務や業務のみを担当するという意味合いになっています。
このような意味から、専任が使われる業務は専門的な知識や技術が必要とされる場合が多く見受けられていて、複数の仕事ではなくひとつの仕事に限定して担当する場合に利用されるケースがほとんどだとされています。
似た言葉である「専従」の意味とは?
これは「従」という漢字に「付属する」「つきしたがう」という意味があるためで、ほかの仕事と並行して従事するのではなく、特定の専門的な仕事や業務を担っている場合に用いられることが多いです。
このため専任と同じように複数の仕事を掛け持ちして行うというケースは少なく、基本的にはひとつの仕事を担当しているという意味合いで利用される言葉になります。
「専任」と「専従」の違い
実際にどちらの言葉も「もっぱらひとつの仕事を担当して従事する」という内容になっているほか、他の仕事や業務と兼任できない場合が多いなど、意味だけではなく用いられる場面もほとんど類似しているのです。
このような点から「専任」と「専従」の違いについてはほとんどないと考えられており、用いられる場面もあまり違いはない傾向が見受けられます。ただ「専任」の方が、担当する仕事に対する責任は若干軽い印象があるという違いはあるようです。
環境によって「専任」と「専従」の意味合いが変わる?
例えば医療機関や介護福祉施設などの医療介護業界の現場、教員などの教育関係の中では、「専任」と「専従」の意味合いや拘束力は異なっているため、注意して仕事内容を確認しなければいけません。
特に医療現場では、「専任」と「専従」は役割が明確に区別されている場合があります。ここからは、そんな環境による「専任」と「専従」の違いについて、医療現場での2つの言葉の意味合いや拘束力の違いについて解説します。
医療現場での「専任」と「専従」の違い
ただ厚生労働省のがん診療連携拠点病院等の整備によると、医療現場における「専任」は「当該診療の実施を終業時間内で5割以上担当していること」に対して、「専従」は「当該診療に終業時間の8割以上従事していること」としています。
このことから、「専任」よりも「専従」の方が指定された業務への従事に対する拘束力が強く設定されていることがわかるのです。
出典:がん診療連携拠点病院等の整備について|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000041483.pdf
「専任」は他の仕事と兼任できる場合もある
これは医療現場によって定義が異なっているところがポイントで、あくまでも指定されている仕事や業務をメインとして取り組み、ある程度手が空いている場合ややむを得ない状況になった場合は他の業務と兼務することができるとされています。
そのため、自分が従事している医療現場での「専任」の範囲を確認しておくことが必要です。
「専従」はその仕事以外できないとされる
これは厚生労働省が定めている施設基準で、「専従」は終業時間の8割以上を指定されている仕事や業務に従事しなければいけないとしていることが理由で、基本的に他の業務と兼任している時間が設定されていません。
そのため「専従」に関しては拘束力が強く、他の業務との兼務が認められていない医療現場が多く見受けられるので、こちらに関しても事前に確認をしておく必要があります。
出典:がん診療連携拠点病院等の整備について|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000041483.pdf
「専任」の対義語
[no_toc]
そんな類義語とは別に、「専任」には意味が真逆となる対義語もあります。「専任」の主な対義語としては「兼任」と「非専任」が挙げられています。「非専任」は専任ではないという意味のほか、その業務や仕事だけ担当していないという意味です。
では「兼任」はどのような意味の対義語になるのかというと、「非専任」とはまた異なる方向での対義語となっています。ここからは、「専任」の対義語である「兼任」について解説します。
「兼任」の意味
医療現場でも同じ意味で用いられており、「専任」または「専従」と指定されている仕事や業務以外は掛け持ちすることができるようになっています。
「専任」は指定されている仕事や業務のみを受け持つことを指しているので、「兼任」は対義語です。ただ医療現場における「専任」の場合は、必要に応じて「兼任」が認められています。このため、医療現場では対義語と定義することが難しい言葉です。
「専任」の意味を理解しよう
類義語である「専従」も同じ意味を持っていますが、医療現場など一部の環境下では「専任」の拘束力は弱くなっているので、環境によって設定されている意味や役割を理解して仕事をしなければいけません。
このような点から、「専任」または「専従」の仕事や業務がある職場で働く場合は、その意味や役割をきちんと把握して対応しましょう。