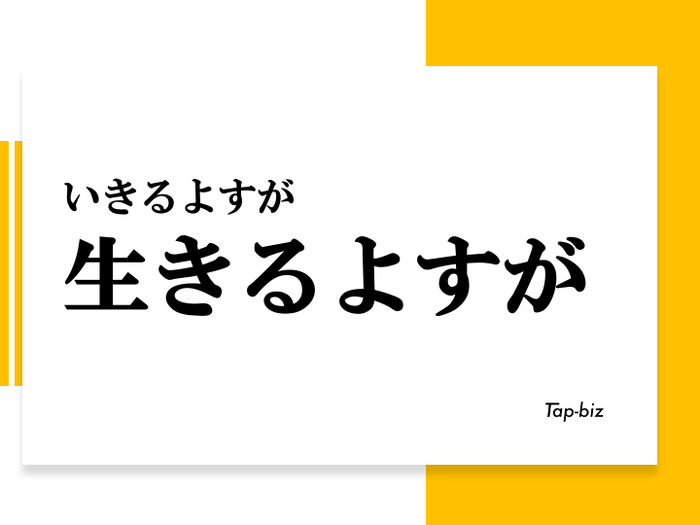[allpage_toc]
「しっかりと意味を理解して言葉を使いたい。」
このように考えている方は多いのではないでしょうか。
社会人にとって言葉遣いは、その人の印象を左右するとても大事なことです。間違った言葉遣いをしていると、相手に良い印象を与えることは難しくなります。
この記事では、「生きるよすが」という言葉に焦点をあて、意味や使い方、似ている言葉などを紹介しています。
この記事を読むことで「生きるよすが」という言葉の意味をしっかりと理解し、正しく使用することができるようになるでしょう。
正しい言葉遣いをしたい、しっかりと意味を理解したいという方は、是非ご覧ください。
「生きるよすが」とはどんな意味?
「よすが」という言葉には、「寄せるところ」や「心のよりどころ」などの意味があります。他にも「頼みのつな」や「故郷や縁」などの意味も含まれています。
「生きるよすが」は「生きていくための心のよりどころ」や「生きていくための頼みの綱」という意味です。
「よすが」の語源・由来
「寄」は「家にいる」という意味を持っています。合わせて「家にいるときのように頼りになるところ」という意味になりました。
「よすが」の漢字表記
漢字では「縁」「便」「因」と表記します。意味はどれも同じです。
「よすが」の使い方・例文
「~をよすがに」
- かわいい子供たちが生きるよすがになっている。
- 友人をよすがに転職をする。
「~をよすがとする」
[no_toc]
- 両親との楽しい思い出をよすがとする。
- 恩師にかけられた言葉をよすがとする。
「よすが」の類語
では、「よすが」と似た言葉にはどんなものがあるのでしょうか。「よすが」との違いを意識しながら確認していきましょう。
手がかり
「手がかり」は具体的な行動を意味することが多いのに対し、「よすが」は手立てや手段といった方法を表す場合が多いです。
共に似た意味を持っていますが、用いる場面が違います。
て‐がかり【手掛(か)り/手懸(か)り】
読み方:てがかり
1 手をかける所。よじ登るときにとりつく所。「—のない一枚岩」
2 問題を解決するためのいとぐち。「捜査の—をつかむ」「問題を解く—がない」https://www.weblio.jp/content/%E6%89%8B%E3%81%8C%E3%81%8B%E3%82%8A
足がかり
「足がかり」は何かを始めるきっかけや糸口という意味があります。「よすが」は手立てや手段の方法を表すもので、「足がかり」とは違う意味になります。
共に似た意味を持っていますが、用いる場面が違うのです。
足がかり
読み方:あしがかり
足を引っ掛ける部分。登攀の取っ掛かりとする。転じて、物事を開始する糸口となるもの。「足掛り」「「足掛かり」「足懸り」とも書く。https://www.weblio.jp/content/%E8%B6%B3%E3%81%8C%E3%81%8B%E3%82%8A
拠り所
「拠り所」と「よすが」は語源は同じです。共に頼りや支えといった意味を持ちますが、「拠り所」は精神的な信頼を示す場合に使われることが多いです。
寄る辺
この「寄る辺」という言葉は否定的な意味でも使われることがあるのです。その場合は「頼りがなくて悲しい」といった感情表現の言葉になります。
より‐どころ【▽拠り所/▽拠】
読み方:よりどころ
1 頼みとするところ。支えてくれるもの。「心の—」「生活の—を求める」
「よすが」の英語表現
「よすが」を「頼みのつな」という意味で使う場合は、英語では「means」という単語を使います。「means」は手段を意味する単語です。
「縁」という意味で「よすが」を使う場合は、数種類の英語表記があります。直訳すると「border」、絆を表現するときは「bonds」、巡り合わせを表現するときは「chance」になります。
「生きるよすが」のように、「よすが」を「心のよりどころ」として使うときの英語表現はありません。
[no_toc]
「生きるよすが」の英語表現
「生きるよすが」は英語では「means of living」で表します。「よすが」は単語で表しましたが、「生きるよすが」は文章での表現になるのです。
「生きるよすが」の類語
「生き甲斐」「心の支え」「生きる意味」「生きる力」など、生きるための力の源となるようなものになります。
「生きるよすが」の意味について理解を深めよう
この記事をきっかけに、「生きるよすが」という言葉を積極的に使ってみてはいかがでしょうか。「生きるよすが」の正確な意味と使い方を理解して、正しい言葉遣いをしましょう。