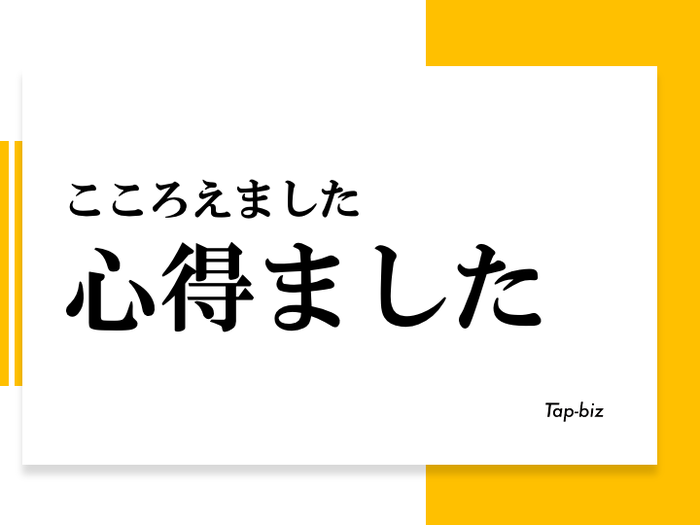[allpage_toc]
「心得ました、という言葉の言い換え表現を知りたい」
「上司の意見に同意するとき、どのような言語表現をすればいいのだろうか」
職場で「心得ました」という言葉を聞いたことはありますか。どのような場面で使えばいいのかわからなくて、疑問を感じている人もいるでしょう。
本記事では、「心得ました」の意味や使い方、言い換え表現についてまとめました。併せて、「心得ました」を使うときの注意点についても解説しています。
本記事を読めば「心得ました」の意味や使い方が理解できるので、ビジネスシーンで使うこともできるでしょう。
本記事を参考にして、ビジネスマナーのアップに役立ててください。
「心得ました」の意味
では、原形である「心得る」の意味を紹介しましょう。主な意味は下記の通りです。
- 物事の事情や意味をよく理解する。のみこむ、わきまえる。
- 事情を十分に理解した上で、引き受ける。承知する。
- 会得している。たしなみがある。
特にビジネスでは「心得ました」という言葉を使用する可能性があります。たとえば、有益なアドバイスを受けたとき、お礼を伝えた上で「今後のために心得ておきます」と締めくくるとよいでしょう。
「心得ました」の使い方
「心得ました」という言葉は、親しい人同士ではなく、ビジネスや公的な場面で使用される傾向があります。ただし「心得ました」という言葉は丁寧語になるので、顧客や取引先、上司や先輩など目上の人への使用は慎重にしてください。
もし、「心得ました」という言葉の使い方を間違ってしまうと、相手に不安や不信感を与える可能性があります。
ビジネスで信頼感を得るためには、日頃の言葉遣いも大切です。「心得ました」という言葉を使うときは注意しましょう。
「心得ました」を使った例文
- 「新しいシステムの扱いは心得ております。ご安心ください」
- 「A様からのご依頼、心得ました。私にお任せください」
- 「華道だけではなく、茶道も少しは心得ています」
「心得ました」の言い換え表現
本章では「心得ました」の言い換え表現を6つ紹介しましょう。いずれの表現も「心得ました」と同じ意味を表しますが、受け手の立場により使用される言葉は微妙に異なります。
つまり、話し相手との間柄や距離感によって、言い換え表現を使い分ける必要があるでしょう。たとえば、話し相手が顧客や上司など立場が上の場合、言い換え表現だけではなく、敬語表現も加わります。
それぞれの言い換え表現の特徴をよく理解した上で、使い分けることが大切です。
[no_toc]
かしこまりました
「かしこまりました」を漢字にすると「畏まりました」になります。ただし、通常のビジネスシーンでは平仮名表記が一般的です。
では、「かしこまりました」は、どのようなシーンで使用されるのでしょうか。たとえば、上司から仕事を依頼されたとき、了解したことを伝えるために「かしこまりました」と返事します。あるいは、メールで返信する際に「A案の件、かしこまりました」と伝えます。
上記のように、顧客や取引先、上司や先輩など立場が上の人に対しては「わかりました」ではなく、「かしこまりました」と答えましょう。
承知致しました
「承知」の意味は主に3つあり、下記の通りになります。
- 事情などを知ること、わかっていること
- 依頼や要求を受け入れること、承諾
- 相手の事情などを理解した上で許すこと
では「承知致しました」は、どのようなシーンで使われるのでしょうか。主には、目上の人や立場が上の人に対して使います。
たとえば、上司から「明日の15時から打合せできますか」と聞かれた場合、「明日の15時ですね。承知致しました」と返答しましょう。
承りました
「承る」の主な意味は、下記の通りになります。
- お受けする。謹んで受ける。
- 拝聴する。謹んで聞く。
- 伝え聞くところによる。
- 謹んでお引き受けする。
次に「承りました」の例文を紹介しましょう。たとえば、顧客からの電話で伝言を受けたとき「私でよろしければ、ご用件を承ります」といった例文が挙げられます。また、顧客から予約があった際に「ご予約を承りました」といった例文もあります。
了解致しました
「了解」とは「よく理解すること、理解して承認すること」という意味があります。ただ、理解するだけではなく、相手に対する承認や同意も含まれています。
「了解」という言葉はビジネスシーンでよく使用されていますが、注意が必要です。実は、立場が上の人が下の人に対して「わかった」ということを伝えるときに使用されています。
したがって、顧客や上司に対して「了解です」と伝えることはマナー違反になるでしょう。ただし、同僚や目下の人には問題ありません。
「了解致しました」という言葉には謙譲語が含まれているので、上司や顧客など立場が上の人に使用することも可能です。
了承しました
主に、目上の人が部下や後輩に対して「それでいいですよ」という意味合いで使用される言葉です。したがって、上司や顧客など立場が上の人に対して使用することは控えてください。
主な例文としては、同僚や部下に対して「A社へのプレゼンの件、了承しました」という表現や「本日の会議の内容、了承していますので安心してください」といった表現が挙げられるでしょう。
丁寧語も敬語の1種ですが、目上の人に対する表現としてはふさわしくありません。敬語を使用するときは、尊敬語・謙譲語・丁寧語、それぞれの特徴を理解することが大切です。
わかりました
もし、立場が上の人に「わかりました」と伝えると、敬意が足りないと思われる可能性があります。ビジネスシーンなど、顧客や上司、取引先の担当者や先輩と会話やメールでやり取りするときは、「わかりました」の使用を避けてください。
「わかりました」の敬語には、「承知しました」「承りました」「かしこまりました」といった言語表現が挙げられるでしょう。
話し相手から好印象を持たれるためにも、適切な言語表現を身につけてください。
「心得ました」を使うときの注意点
「心得ました」には、ただ「わかりました」という意味ではなく、「よく理解して、記憶しておく」という強いニュアンスがあります。たとえば、ビジネスシーンで「心得ました」と伝える場合は、気をつけて使いましょう。
また、「心得ました」を使うときは「使用する相手」にも注意してください。「心得ました」という言葉は丁寧語になるので、上司や顧客など目上の人への使用は控えましょう。
目上の人に使用する場合は、「承知致しました」や「かしこまりました」といった表現が適切です。
「心得ました」の正しい使い方や言い換え表現を理解しよう
[no_toc]
自分では正しいと思っていても、間違った使い方をして、知らぬ間に不快感を与えているかもしれません。もし、ビジネスシーンで使ってしまうと、顧客や取引先、上司や先輩に不信感や不快感を与えている可能性もあるでしょう。
ビジネスシーンでは、正しい言語表現は大切なスキルの1つです。曖昧な知識で、何となく言葉を選ぶのではなく、それぞれの言葉の意味を十分に理解した上で、使う姿勢が求められます。
言葉の意味だけではなく、使用されるシーンや敬語の有無についても十分に調べるよう心掛けましょう。