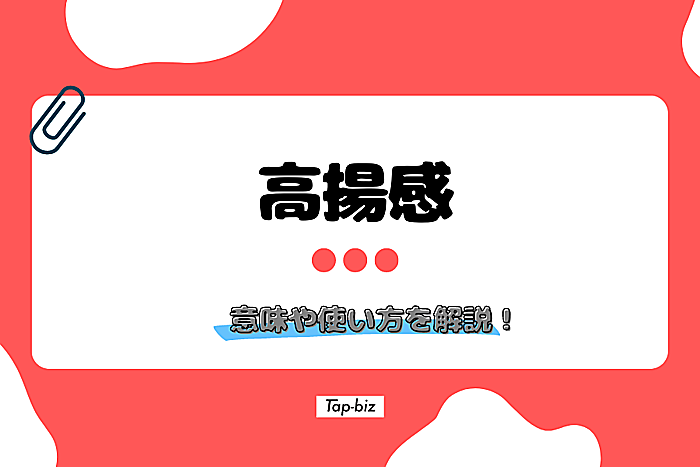[allpage_toc]
本記事では、高揚感の意味や使い方、類語などに加え、使用するうえで気をつけるポイントについて詳しく説明します。
この記事を読めば、高揚感という言葉を正しく理解し使いこなせるようになります。ビジネスシーンなどで使用すれば、知識や教養の高さを印象付けることもできるでしょう。英語訳も紹介しているので、英語を使う人にとってもボキャブラリーが増えます。
高揚感の意味を知りたい方や、語彙力を高めて表現の幅を広げたい方は是非この記事をチェックしてみてください。
高揚感の意味と読み方
通常、好きな音楽を聞いたときや受験に合格したとき、スポーツスタジアムでの試合観戦など、嬉しさ・楽しさ・喜びといったプラスの感情に対して用いられます。
普段の会話のなかであまり使用されることはありませんが、テレビ中継などで客観的に状況説明する際にはしばしば用いられる単語です。
高揚感の由来
「高」はそのまま高さを表し、後に続く言葉の程度が高いことを意味します。「揚」は訓読みで「あげる・あがる」と読み、物理的に低いところから高いところへ移るさまを表します。
したがって、高揚とは「(通常より)高いところへあがっている」という状態を表し、状態や感情に対して用いられると「興奮」や「たかぶる気持ち」という意味になるのです。
高揚感の使い方と例文
一般的に「高揚感がある・ない」という表現はあまりなく、覚える・包まれるなど他の動詞と組み合わせて使われます。よく使う表現を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
高揚感は、前述のとおり話し言葉よりもフォーマルな場で用いられることが多い言葉です。目上の方などを相手に状況説明する際に違和感を抱かれることのないよう、正しい使い方と例文を覚えておくとよいでしょう。
高揚感を抑える
そのため、冷静でいるように努める必要があるときや、反対に否定表現を用いて冷静でいられないほどの興奮を表したいときに「高揚感を抑える」を使うとよいでしょう。
- 仕事中にライブの当選メールが来たので、顔に出ないように高揚感を必死で抑えた。
- 応援していたチームが優勝して高揚感を抑えられなかった。
高揚感に包まれる
「包まれる」は物が覆われている状態を指し、感情表現と一緒に使うことで「ある感情でいっぱいに満たされている」という意味になります。
一般的には自分の状態を表すというよりも、他者、特に大勢の人々が同様の興奮状態にある状況を描写するのに用いられます。
- サッカースタジアムは熱気と高揚感に包まれています。
- ライブから帰ってきた娘は高揚感に包まれていた。
高揚感が高まる
楽しみにしていた旅行や好きなミュージシャンのライブなど、前日から寝付けないほど興奮しているような状態は既に「高揚している」と言えます。当日にはさらにボルテージが上がり「高揚感に包まれる」状態に達しますが、その過程で興奮が徐々に増していく様子が「高揚感が高まる」なのです。
- デートのために新しい服を着たら高揚感が高まってきた。
- 会場の高揚感はライブの開始とともに高まり、クライマックスで最高潮に達した。
高揚感を感じる
[no_toc]
ただし「〇〇感を感じる」は誤った表現ではないものの「頭痛が痛い」「友達たち」と同様の二重表現のように見えてしまい、人によっては違和感を抱きかねません。高揚感の自覚を表現するときは次の「覚える」を用い、「感じる」は例文のように倒置的に使用するのが無難です。
- 新しく買った時計が目に入るたびに感じる高揚感。
高揚感を覚える
自分にとって気持ちが明るくなるものや興奮することを想像してみてください。それらを他の誰かに説明するとき、「私は〇〇で高揚感を覚える」という表現がぴったりです。
- 私が高揚感を覚えるのは、ミステリー小説を読み進めてクライマックスが近づいてきたときだ。
高揚感を得る
落ち込んだとき、気分を上げるために音楽を聞いたりショッピングをしたりすることがあるでしょう。そのおかげで気持ちが高まったとき「高揚感を得た」と言えます。
- 良質なステレオでオーケストラのサウンドを聴き高揚感を得る。
高揚感に浸る
「〇〇に浸る」という言い回しは否定的にも使い、必要以上に長くその状態に入りきっていることを表現できますが、使用するときは相手に誤解を与えないように注意しましょう。
- ライブから帰った後も冷めやらぬ高揚感に浸る。
高揚感の類義語と言い換え
高揚感の意味にもあるように「興奮」は同様の意味で用いることができます。興奮の度合いが高くなると「熱狂」という表現がぴったりです。高揚感を用いるとやや堅い表現になりますので、これらの言葉の方が気軽に使えます。
また、より砕けて口語的に表現すると「テンションが高まる」となります。場面に応じて使い分けができるとよいでしょう。
昂揚感
高揚感と同様の使い方ができるので、前述の動詞との組み合わせはすべて「昂揚感」に置き換えることができます。
高揚感を使う時の注意点
文章表現において高揚感という単語が使えると知識や教養をアピールできて好印象になりますが、一歩間違えると相手に誤解を与えることもあるので、正しい使い方ができるよう下記を参考にしてください。
[no_toc]
高揚感が使える状態を見極める
また、精神的な不調によって意図せず興奮してしまう状態に「高揚」が用いられることもあります。前後の文脈や言い回しによってはこれらの意味に捉えられ得るため十分に気をつけましょう。
多幸感とは使い方が異なる
しかし、「多幸感」は主として薬物により自分では制御できない過度な幸福感のことを指します。高揚感とは全く意味の異なる使い方をするため、言い換え表現として誤って使わないように注意してください。
高揚感の対義語は?
高揚感とは気分が高まるような感情・感覚を表していました。したがって反対の意味を考えると、気分が下がったり落ち着いていたりするような状態ということになります。
新たな言葉を習得する際には対義語も覚えると、より理解が深まります。ぜひ参考にしてください。
消沈
冷静
「冷」には感情が高ぶらないように落ち着かせるという意味も含まれているため、前述の「高揚感を抑える」を「冷静」と言い換えることもできます。
高揚感を意味する英語は?
高揚感と直訳するならば、elationという単語がぴったりです。他にも、熱狂や興奮といった意味をもつexhilaration・enthusiasticなども気持ちの高ぶりを表現できます。この3つの単語について詳しく紹介していきます。
Exhilaration
experienceやhaveなどの動詞を用いて「高揚感を味わう」と表現したり、「exhilaration of 名詞」という形で「(名詞)の高揚感」と表したりします。
Enthusiastic
[no_toc]
すでに気持ちがたかぶっているさまを表すため、高揚感の訳語として使用する際には「高揚感に包まれる」「高揚感に浸る」というニュアンスが適しています。
Elation
高揚感の使い方で紹介した「感じる」「高まる」などの動詞を表す英単語と組み合わせることで、日本語と同様の言い回しができます。
高揚感の意味や使い方を理解しよう
ただし、「高揚する」という言葉には依存性や不安定さを内包したネガティブな意味もあります。思わぬ誤解を招く場合もありますので、使う状況や文脈には十分注意してください。
高揚感の意味や使い方を正しく理解し、文章表現の幅を広げましょう。