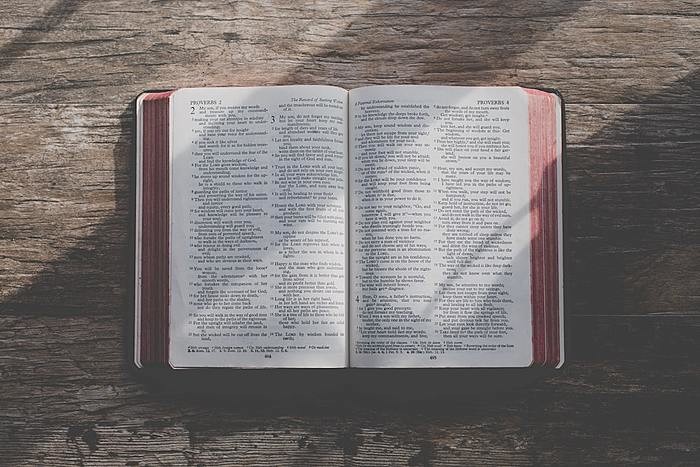最後の願いは叶う
「猿の手」では、1番目と2番目の願い事は望まない形で願いが叶います。そして、必ずと言っていいほど3番目の最後の願いは、元に戻してほしいという願いです。これは、民話やおとぎ話に出てくる3つの願い方式のお約束です。
しかし、この「猿の手」は教訓を教えるためだといえ、願い事の叶え方は少々理不尽に感じます。ささやかながらも幸せな一家が、結局は最後は平穏な元の生活に戻りますが、ちょっとした欲のために代償として大切なものを失う様子は、悪魔に付け込まれたように思えます。
「猿の手」の教訓とは欲を出すことの愚かさについて教えているようにみえますが、もしかすると厄災や災厄の事についての教訓を示唆しているように見えます。なぜなら、これらは幸運に隠れてやってきたり、呼んでもいないのにやってくるからです。
息子はどんな状態だったのか
息子の生き返りを望んだのは妻であり、夫は反対していました。なぜなら、夫は息子の最後の姿を見ていたからです。そして、ここで疑問が沸きます。それは、夫が生前の健康の状態の息子ではなく、死んだ直前の息子を想像しその状態で生き返ったと思ったことです。
これは、ドアを開けていれば確認できたことです。しかし、結局3番目の願いで元に戻ってしまいます。このような想像力を刺激しているのが、この「猿の手」の醍醐味です。読んでみると、いろんなところに想像力を刺激する伏線があるので、一度読んでみてください。