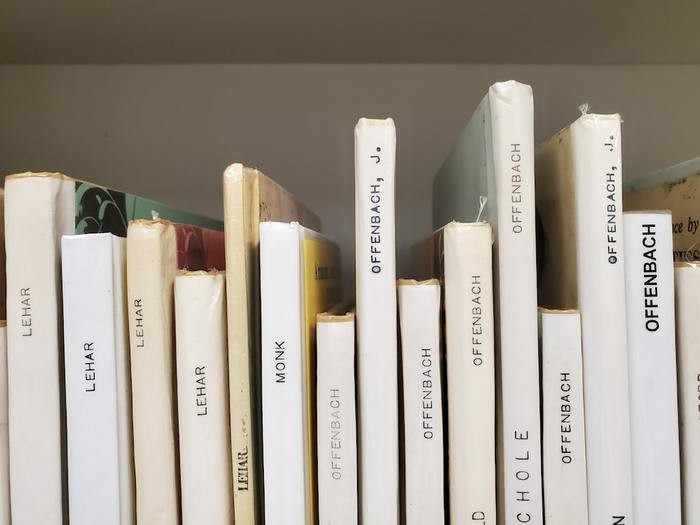ここでは具体的に、報告書の例を記したいと思います。このフォーマットはレポートの書き方の基本的を押さえてあるもので、参考にできるものとなっています。
日付平成◯年×月×日
制作者 ××部××課 山田太郎
20××年×月度業務報告
20××年×月度業務報告内容及び成果につき、下記の通り報告いたします
記
1 業務報告
わが社の製品は、取引先に高評価を得て売れ行きは増加の一途をたどっている。云々
今回は新製品の売り上げ推移を報告する。
2 業務成果
売れ行きは下記の通りである。
月間売り上げは××万円で、先月よりも10%の伸びを記録した。
詳細なデータを表示
3 今後の目標、展開
今後も取引先であるA社やB社は、今回の新製品以外にも、既存製品を納入したいと考えている。今後も受注が望まれる。よって、○○工場の生産を強化する必要性がある。
4 所感
さらなる開発を進め、今後も他の製品が受注できるよう、低価格化も考えなければならない。
資料 売り上げ推移表
おおざっぱではありますが、これが業務報告書の流れです。企業によっては会社指定のフォーマットがあるでしょうが、基本は同じです。まずは、報告する内容とその結果(成果)を簡素に書くことが重要になります。
引用の記載方法
レポートを書く上で必要になるのは、参考資料です。レポートを作成する上で、参考にした資料を記す必要があります。もちろん引用にも必要です。引用の記載方法は主に2種類あり、レポートの書き方の重要な部分でもあります。
文章の途中に括弧
この方法は注釈、引用、参考文献の出典記載も区別なく本文中に小さな括弧があり、そこには通し番号が振られています。章末や巻末にその通し番号順に記載されています。
文章の途中に括弧の特徴
文章の途中の括弧式の記載方法の長所として、文章を読む際に邪魔にならないという点です。この方法は読み手に対してストレスを感じない引用の記載方法です。また、この方法は古いと言いますか、従来の引用記載方法でもありますが、レポートの書き手として、複雑で慣れるまで時間がかかるという点があります。
本文中に大きく記載
この方法は本文中にあらかじめ大きく記載します。例えば注釈ならば(注1)といった具合です。参考文献ならば(本のタイトル、著者名)といった感じです。引用ならば(本のタイトル、著者名、ページ番号)です。
本文中に大きく記載の特徴
本文中に大きく括弧を付けて引用していく記載方法は、書き手にとってとても簡単だということが大きな特徴です。文章を書いているその都度その都度、出典元や引用元を記載していけばいいので、後々参考元や引用元がわからないということがありませんし、簡単です。修正も通し番号の必要がないので、修正も楽。しかし、読み手にとっては邪魔になります。
文献表示方法
レポートは資料を元に書いていくわけですが、参考文献の表示は(著者名、出版と発表年)ですが、引用元は(著者名、出版と発表年、引用ページ)になります。引用はそのまま参考資料の文章を書き写すので、引用ページ部分を必ず記載しましょう。
そして、参考文献、引用の記載方法を2種類紹介しましたが、絶対に一緒に使ってはいけません。どちらかの記載方法でレポートを作成してください。
インターネットの記載方法
資料の集め方は近年ではインターネットを使うようになってきました。インターネットも引用したり、参考にした場合は記載しなければなりません。インターネットの記載方法として下記の通りです。
<参考URL>
参考サイト名
URL(アクセス日○○年×月×日)
となり、参考にしたサイト名とURLの記載の他に、アクセス日の記載する必要があります。
いいレポートを作るにはいい「問い」を立てること
今回は大学生向けと社会人向けのレポートの書き方についてまとめてみました。この記事を読んで、レポートの体裁をしていることに気づいたでしょうか?
まずテーマである「レポートの書き方」があり、序論部分となるレポートの書き方についての問いの設定。本論部分は、大学生向けや社会人向けのレポートの書き方についての説明になり、結論はまとめ部分となっています。引用は文章中に大きく記載する方法をとっています。
今回の記事は本来出題されるレポートの課題とはかけ離れています。よって、テーマが与えられているけれど、うまくレポートを書けないという人は結構います。そういう人はテーマから「問い」を立てる考察部分が苦手な可能性があります。
しかし、この問いの設定をすれば、どのようなアプローチでレポートを書いていけばいいのかわかります。今回紹介したレポートの書き方の参考文献には、「問い」の設定方法についての詳細も紹介しているので、自身に合う本や、まずは問い設定すると意識をもってレポートを書いてみてください。