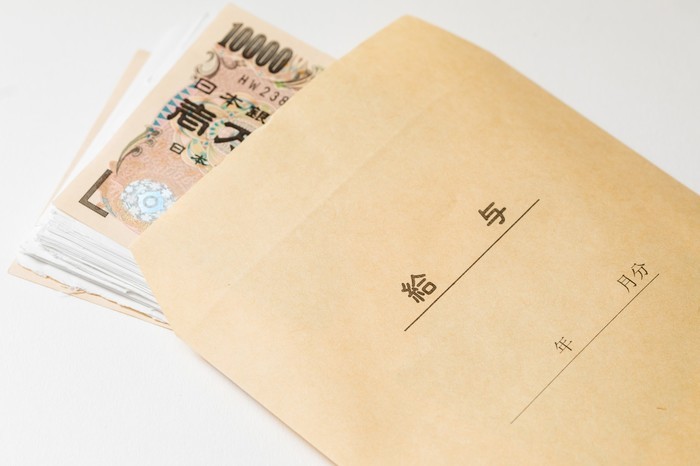職責とは
皆さんはビジネスシーンにおいて、「職責」という言葉を耳にしたことはありますでしょうか。ビジネスシーンではビジネスマナーと同じようにさまざまなビジネス用語が活用されていますが、当たり前のように使っているけれども本当はあまり分かっていないというのも、実はビジネス用語です。
今回はその中でもこちらの「職責」という言葉に関することについて、「職責と」よく間違われて使われやすい言葉やそれぞれの意味合いについてなどについても、詳しくご説明してまいります。
職責とは何か
まず職責についてご説明いたしましょう。職責とは一言でいえば「職務上の責任」のことを指します。仕事にはそれぞれの立場で果たすべき職務とそれらに伴い責任が生じます。
行政や人事制度が確立している中堅企業であれば、それらの役職ごとの職務上の責任が明文化されているので、どこまでが職責なのかが分かりやすくなっています。たとえば会社の定款や規則、規定集、職務分掌表などがそれにあたり、部長、課長、係長、主任などとそれぞれの役職に対して職責が明記されているのが通例です。
これまでの説明でお気づきの方もいらっしゃると思いますが、職責と職権はワンセットであり、職責を担う役職ということは、つまりはそれぞれの役職に応じた権限が発生するということになります。
平社員には職責はない?
では役職が付いている場合は職責をイメージしやすいですが、役職などがない平社員には職責は発生しないのでしょうか。よく平社員は権限もないから職責も発生しないと考えている方がおり、これは特に新卒社員や若手社員に多く見られる考えです。
しかし結論としてはそんなことはありません。どの立場であってもそれぞれの立場によって、割り振りされた仕事があり、その仕事を責任をもって遂行するべきであり、そこには職責が発生するのは仕事である以上、当然のことです。
一般的には職務分掌表によって、与えられた仕事を責任をもって遂行する義務があるとされており、役職がない社員や一般職員にも職責はあるものです。
職責を全うするには
残念ながら、企業には職責について明記されているところもあれば、明記されていないところもあります。特に係長やリーダー職などの中間管理職と呼ばれる職位にははっきりと明記がない場合が多々ありますが、明記されていないからと言って職責がないわけではありません。
立場上その部署などを統括する責任者である以上、部下の仕事の管理や決定権を持っているわけですから、中間管理職にも職務を全うする責任はあり、当然ながら部下よりも権限がある以上、部下よりも職責は大きなものとなります。
職責を全うするためには、まずは自分の立場での職責とは何か、企業から自分の職位で求められていることは何かをしっかりと理解し遂行することが、まずは職責を全うする第一歩であるといえます。
そして、与えられている任務、仕事の範囲内でどれだけ最善の行動ができるかを考え、常に最善の結果を出せるようにまい進することが、結果として職責を全うすることに繋がるのです。
ちなみに「職責を全うする」という言葉には「責任を取る」という意味合いもあります。ですから、職責を全うする、ということは、万一現場で何かトラブルが起きた際や部下がトラブルを引き起こした際には、その責任を取って行動することができるというのが「職責を全うする」ということになるのです。
なお、行政の場合は一般職員であっても主事や主事補という資格があり役職として与えられますので、職責や役割を形に表していると考えられます。
職責手当や職責給とは
それでは今度は「職務手当」と「職責給」についてです。たとえば企業の募集要項に「職務手当」や「職責給」などと記載されたものがありますが、それぞれの意味についてはご存知でしょうか。こちらも同様に、それぞれについて詳しく見てまいりましょう。
職務手当とは
まず職務手当についてご説明いたします。
職務手当とは、一般的に「特別な技術や技能、または資格などを必要とする職務、または企業が必要と認めた職務を遂行する者に払われる手当」のことを指します。
ですが稀に企業が残業手当と混同し、「残業をするくらい特別な仕事をする」というニュアンスで職手当=定額の残業手当と定義している企業もあります。
職責給とは