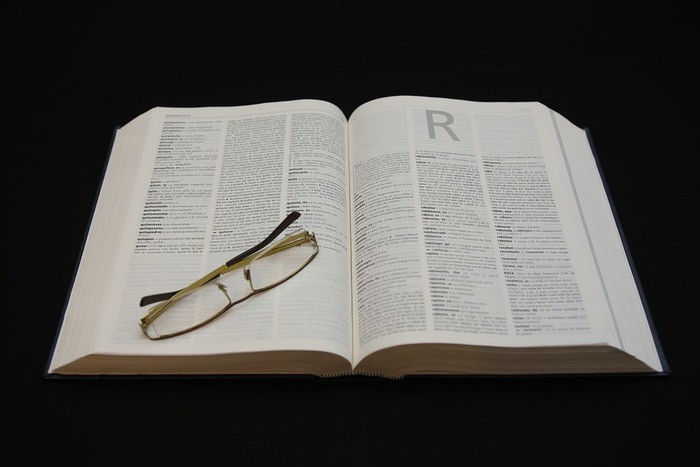関西弁の方言「ダボ」ってどんな意味?
関西弁には「ダボ」という言葉があります。あなたはどういう意味かご存知でしょうか。この「ダボ」という言葉、意味を知っている人からすれば、胸を張って紹介できるかと聞かれると、実は少し自粛したい気持ちがする言葉だとも言えます。
そのわけは読み進めて行っていただけると、おいおいお分かりいただけることでしょう。とにかく関西の「ダボ」を使うエリアでは、昔から老いも若きも普通に使ってきた「アホ」や「バカ」に意味のよく似た方言で、この先無くなることは考えられない聞き馴染みのある言葉でもあります。
それでは関西の特殊な方言の一つでもある「ダボ」ワールドに、あなたをご招待させていただきましょう。
「ダボ」は大阪の言葉?
「ダボ」という言葉は、関西弁でも実は少し特殊であると言っていいでしょう。なぜなら関西弁の代表格である大阪の人の間では、あまり使われていないからです。
大阪では「アホ」や「ボケ」は使っても、「ダボ」はあまり聞こえてきません。「ダボ」は関西弁と言っても、実は兵庫県の南西部を主とする言葉になり、「アホ」<「ボケ」<「ダボ」といった順位付けの言葉になります。
アホとは違うの?
関西弁でよく使われる言葉に「アホ」という言葉があります。この「アホ」には、関東でいう「バカ」と似た意味があります。では「ダボ」とはどういう意味があるのでしょうか。
「ダボ」は、「バカ」や「アホ」と似た意味を持っています。ただし、関西では「バカ」は気持ちを表現する言葉として選択されにくいので、一般的には「アホ」に近い意味と言えるでしょう。
ただし「ダボ」は「アホ」より激しい気持ちが込められることが多くなります。「アホ」では気持ちが満たされない、「ボケ」でも表現しきれない、そんな時に使われるのが「ダボ」という言葉であることが多いです。
そして「アホ」は男女同じくらいの頻度で使いますが、「ダボ」は意味は似ていても、品の問題から男性が使うことが圧倒的に多くなります。
「ダボ」が使われる地域とは?
「ダボ」という言葉は、関西でも一部尼崎方面や、明石から姫路を中心とする兵庫県の南西部で頻繁に耳にします。神戸については、使う地域と使わない地域が混在していて、使わない人は、全く使うことがありません。
「ダボ」という言葉を知っている人からすれば、「ダボ」を使う人というのは、ガラ(品)のあまりよろしくない人という認識があるのではないでしょうか。それくらい「ダボ」が使われる時の印象は激しく、ガラ(品)の悪い印象を与えてしまいます。
播州弁というのがあるらしい
関西でも加古川・高砂・姫路といった南西部には、播州弁という方言が使われる地域があります。この播州弁と言う言葉は、全国的にもよくガラが悪いと言われる方言として有名です。
この播州弁を使いこなす地域では、「ダボ」は非常によく聞こえてきます。やはり「ダボ」という言葉は、ガラの悪い部類の言葉と言えるでしょう。
例えば「ダボ」は、親であれば女の子にはできれば使ってもらいたくない言葉の一つであるはずです。ですが播州地域ですくすくと育つ子供にとっては、「ダボ」は知らない言葉にはなるはずもなく、必ず知るところとなります。特に男の子同士がケンカになれば、必ず出てくる言葉の一つと言えるでしょう。
「ダボ」の意味の語源や由来を紹介
「ダボ」は、主に人を罵る意味に使われます。「ダボ」を放つときの気持ちは、「アホ」を大きく上回った強いものになります。音楽の記号で表現すると、「アホ」が「フォルテ」なら、「ダボ」は「フォルティッシモ」といった具合です。そもそも「ダボ」にはどんな語源・由来があるのでしょうか。
ドアホ説
一番有力な説としては、関西弁の「アホ」のさらに上をいく「ドアホ」が、「ダァーホ」となり「ダボ」へ変化したという説です。この場合意味合いがほぼ一致しますので、初めて聞かれる方にも意味合いが伝わりやすいのではないでしょうか。
おだぼ説
もう一説は、明石の方面での説が有力です。昔明石藩家老に織田伊織という人がいて、その息子に織田保という人がいました。
明石に住む町人の間では、この織田家はあまり評判が良くなかったらしいのですが、やはり権力には逆らうことができません。表立って文句や悪口を言うわけにもいかなかったため、人々はこの織田家の息子「織田保」のことを、「おだぼ」と陰で呼び、悪口を言っていたそうで、それがいつの間にか「ダボ」につながったという説です。
この場合の「ダボ」の意味は、印象としては少し弱めですが、人を罵るという意味では、あながち全く関係のない話とも言い難いものがあります。
いつ頃から使われるようになったの?