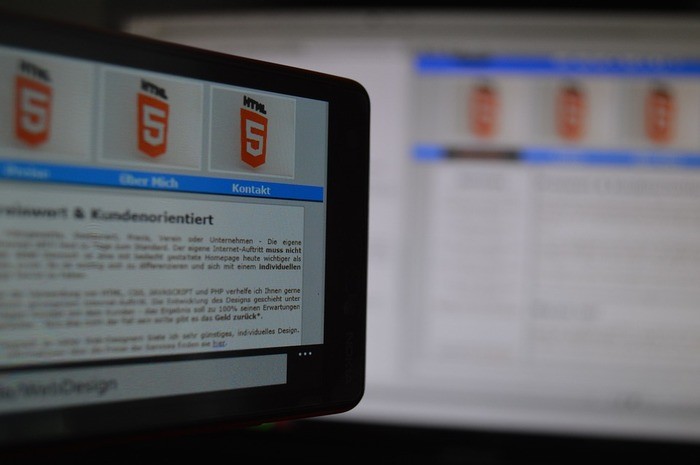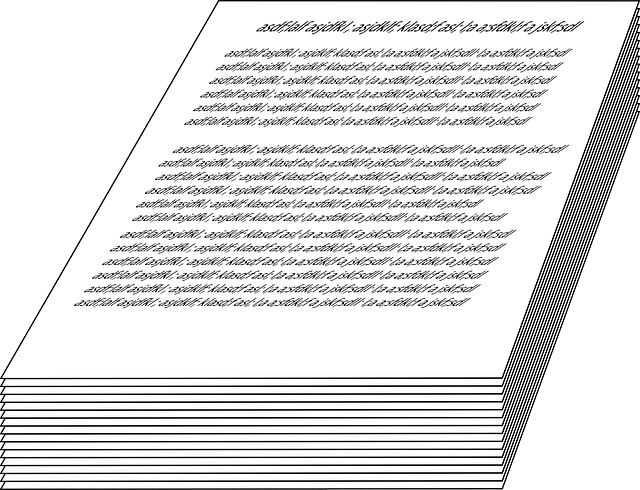①. レポートの場合
高校や大学、大学院の授業では、レポート課題が課される場面が多く存在します。レポート課題における引用元としては、書籍や論文、webサイトがメインになります。本文中や図表中で引用する場合は先述の説明を参照ください。レポート課題で引用した場合には、必ずレポートの最後に出典元を記載します。
出典元の文献を引用した順番に並べて引用番号を振りましょう。なお本文中で引用した箇所には、対応する引用番号を記載するようにしましょう、引用番号のフォーマットについては、一般的には括弧を用いて記載するのが一般的でしょう。以下に出典の書き方の例を紹介します。
例:
(本文中の場合)○○については○○であると定義されている1)。
(レポート文末:書籍の場合)
1). ○○(著者①), ○○(著者②), ○○(著者), 他:本タイトル名, 出版場所, 出版社, 刊行年, 該当ページ
②. 卒論の場合
卒業論文執筆の場合には、研究背景や考察を記載する上で、出典を書く必要がある場面は多くあります。基本的な出典の書き方については、レポート課題と大きく変わりはありません。当然レポート課題の時よりも、文章量が多くなるため、多くに出典が必要になることが予測されます。本文中の書き方としては、まず自身の意見を述べた上で、引用文献を紹介する書き方が良いでしょう。以下に書き方の例を紹介します。
例:
本研究の結果から○○であることが推察される。先行研究では、○○らによると、△△は××であることが示されている。本研究結果は□□らの先行研究を支持しており、■■であるとことが明らかになった。
また研究背景などの紹介にあたって、先行研究の図表を用いることがあるでしょう。こちらの基本的な書き方については、前述に記した出典の図表の書き方の項を参考に記載すれば問題ないでしょう。
例:
本邦における○○は深刻な一途をたどっており、対策は急務だといえる。××の調査では△△について□□であることが示された。1)(図1)。
※1)の部分は引用番号
③. 論文の場合
当然、論文を作成する際にも、引用元の出典を記載することは必須となります。基本的な書き方は、卒論やレポートの書き方を参考にすれば問題ないでしょう。
論文で特に大事になるのは、出典の書き方が適切に投稿ジャーナルの投稿規定に則っているかが重要になります。多くのジャーナルでは、データファイルの体裁、論文の構成や図表の扱い、倫理の書き方、投稿料、出典の書き方が投稿規定として集約されています。投稿規定は基本的には、ジャーナルの巻末や公式サイトに掲載されているため、執筆前に投稿規定を確認した上で書き始めましょう。
なぜ投稿規定の確認が必要かというと、ジャーナルによって微妙に書き方が違いことがあるからです。具体的には、①引用番号の書き方、②著者の書き方(書くべき共同執筆者の人数)、③ピリオド、カンマ、コロンの位置や適用、④出典の書き方の順番などが異なることが多いでしょう。
例えば、著者名を全員記載するジャーナルもあれば、3名のみを記載し残りを「他」として書き方を指定するジャーナルもあります。また、出典元の引用番号の体裁についても、ジャーナルによって異なります。一般的には、)や[]、括弧を用いないことが多いでしょう。ジャーナルに合わせて適切に用いましょう。
例:(書籍の場合)
1). ○○(著者①), ○○(著者②), ○○(著者), 他:本タイトル名, 出版場所, 出版社, 刊行年, 該当ページ
[1]. ○○(著者①), ○○(著者②), ○○(著者), 他:本タイトル名, 出版場所, 出版社, 刊行年, 該当ページ
webサイトの関する出典の書き方
weサイトの記事を記載する際においても、書籍やレポート、論文と同じく出典の記載が必要です。出典の記載方法については、論文などと同じく記事の最後に引用リストを添付してもよいでしょう。また他のwebサイトからの引用の場合には、web サイト名、URL、アクセス日を記載する他に、リンクを張っておくのも良いでしょう。
他のwebサイトからの引用をする際に注意しなければならないのは、引用元のwebサイトが転載を許可しているについてです。一部のサイトでは、「無断転載禁止」と書かれている場合があるため、掲載に当たっては十分に注意するよう心掛けましょう。
種類別に見た出典の書き方
大まかな出典の書き方については、前述の項目にならえば問題ないでしょう。しかしながらレポートや卒論、研究論文などの場合に書籍のみを引用することは少ないでしょう。多くの場合は政府機関のwebサイトからの情報や原著論文などから引用し、出典を記載します。この項では、書籍、原著論文、webサイトについての出典の書き方の一般的な例について紹介します。
①. 書籍の出典の書き方の例
1). 著者名①, 著者名②, 著者名③. 他: 書籍タイトル. 出版場所, 出版社, 刊行年, 該当ページ
②. 原著論文の出典の書き方の例
1). 著者名①, 著者名②, 著者名③. 他: 書籍タイトル. ジャーナル名. 巻号: 該当ページ, 出版年
③. webサイトの出典の書き方の例
1). 掲載元(内閣府など). ページタイトル, URL, アクセス日時
なおこれらの例については、あくまでも一般的な書き方になります。実際の執筆の際には、投稿規定を十分に確認しましょう。
必見!英語論文の出典の書き方
大学の学部学生や大学院生では英語で論文を書くことがあるでしょう。英語の出典の書き方は基本的には基本的には変わりません。出典元の文献が英語になるくらいですから、臆することはありません。こちらでは、英語論文における出典の書き方の特徴について説明します。
英語論文と日本語論文との共通点
前述で述べたように、出典の書き方の注意点はほとんど共通しています。英語論文についても当然投稿規定があり、出典の書き方におけるフォーマットが決まっています。一般的には、「Instruction for authors」、「Information for Authors」といった名称が使用されることが多いでしょう。これらの情報は、ジャーナルのHPや雑誌の巻末に掲載されているのであらかじめ確認しておきましょう。
英語論文における出典の書き方の例
出典に書くべき内容は基本的には日本語と変わりありません。違う点としては、日本語では著者を省略する際に「…他」と記載していましたが、英語論文の書き方の場合には「…et al.」となります。「et al.」のピリオドの記載を忘れる場合が多いのて注意しましょう。
例:
1). ○○(著者①), ○○(著者②), ○○(著者), et al. :タイトル名, ジャーナル名, 巻号, 該当ページ, 出版年
英語論文に日本語論文を引用する場合
基本的には、英語論文の出典は英語ジャーナルや書籍から選択するのがベターでしょう。しかし、日本語論文についても、英語表記に変更することで引用することが可能な場合があります。こちらについては、投稿するジャーナルによって扱いが変わることが予測されるため、事前に投稿規定に確認する必要があるでしょう。この項では、一般的な英語論文における日本語論文の出典の書き方の例を紹介します。
例
1). 著者名(ローマ字表記), et al.: 論文タイトル(ローマ字表記、もしくはタイトルの英訳). ジャーナル名(ローマ字, 正式名称がある場合はそちらを記載). 巻号: 該当ページ, 出版年.